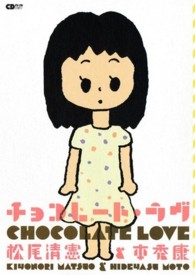出版社内容情報
人間のからだの中でも軽く見られがちな胃や腸.しかし,これらの器官は,食物の成分をすばやく認識したり,毒素の排出を指令するなど,脳と同じ原理で絶妙な働きをしている.消化器ホルモンの研究で主導的な役割を果たしてきた著者が,酒が胃を強くする話など意外なエピソードをまじえながら,知られざる腸の働きとその素晴らしさを語る.
内容説明
人間のからだの中でも軽く見られがちな胃や腸。しかし、これらの器官は、食物の成分をすばやく認識したり、毒素の排出を指令するなど、脳と同じ原理で絶妙な働きをしている。消化管ホルモンの研究で大きな成果をあげてきた著者が、酒が胃を強くする話など意外なエピソードをまじえながら、知られざる腸の働きとその素晴らしさを語る。
目次
1 腸は小さな脳である
2 神経かホルモンか―消化管ホルモン研究の盛衰
3 センサー細胞の発見
4 ホルモンに魅せられた人々
5 下痢の元をたずねて
6 瀬木の帽子
7 臓器を大きくする消化管ホルモン
8 ひろがる細胞の輪―パラニューロン
9 腸のセンサー細胞のルーツを求めて
著者等紹介
藤田恒夫[フジタツネオ]
1929年東京に生まれる。1954年東京大学医学部卒業。1959年同大学院修了。専攻は顕微解剖学、内分泌学。現在、日本歯科大学新潟歯学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のっち♬
127
消化管ホルモンの研究で大きな成果を上げてきた著者が語る知られざる腸の働き。本書で扱う大発見は、消化管上皮系に分布する基底顆粒細胞が上端部を内腔に出して化学情報を受け取り、下端部でホルモンを開口放出する働き。これは身体中の「感覚細胞」「受容分泌細胞」と併せて基本設計上パラニューロンとして見ることが出来、外界刺激を信号変換して内へ伝える生涯絶え間ない原始性へ還元することで、神経とホルモンの連続性や進化論において新たな視野を提供した。「脳は腸からはじまった」—1991年発刊でもヒドラから到達する考察は未だ鮮烈。2023/09/17
神太郎
34
つい最近NHKのヒューマニエンスで腸の凄さを見ていて、はたとこの本の存在を思い出す。書かれたのは30年ほど前。書かれてる内容はそこからさらに時間を遡る。今でこそ番組の一枠まるまるを使わせてもらえている腸も扱いはぞんざいだった。それが神経やらホルモンの存在が実証されてくるに連れじょじょに表舞台へと姿を表すようになる。その悪戦苦闘を演じた学者さん(著者含めた名だたる教授たち)のエピソードを交えて話していく。思い出話がメインだが、読んでいてなかなか面白かった。ある種大学の講義を聞いてる時の感覚に近い読み口だ。2021/07/30
Machida Hiroshi
13
先日藤田紘一郎さんの腸の話を読んでいたところ、腸つながりで本書を紹介されたので読んでみました。面白いもので、本書には腸内細菌叢の話は一切出てきません。しかもかなり学術寄りの内容です。それでも面白く読めたのは、著者の人柄と、それに呼応して周りに集まる研究者、ライバルたちとの交流の様子が実に楽しく描かれているからでしょう。科学者の生態というものが少しわかった気がします。本書で特に印象に残ったのは、腔腸動物のヒドラから枝分かれして進化した進化の頂点の片方は哺乳類ですが、もう片方の頂点は昆虫だということです。2015/06/17
デビっちん
13
考えることができるのは脳だけではない。食物の成分を瞬時に認識したり、毒素の排出を指令するなど、脳と同じ原理を腸は持っている。腸は小さな脳であるだけでなく、脳は腸から始まった。腸を包むニューロンが発達して脳になった。神経とホルモンは対立的なものではなく、連続的な存在である。腸が思考することを考えれば、腸が喜ぶ食べ物を食べ、腸に幸せになってもらおう。たまには断食をして、腸にしっかりと休んでもらおう。2015/08/10
ochatomo
10
胃腸は機械的・化学的刺激を感じ取って、ホルモンを作り基底顆粒細胞から分泌して、消化を制御している 0.4%塩酸→S細胞→セレクチン アミノ酸・卵黄・トリプシン阻害剤→M細胞→CCK 肉エキス・エタノール・重曹水→G細胞→ガストリン ゲリゲン物質・濃いぶどう糖→EC細胞→セロトニン 1991刊 2010/11/24