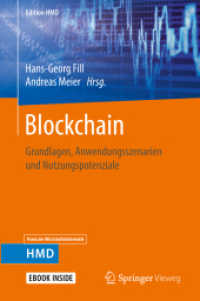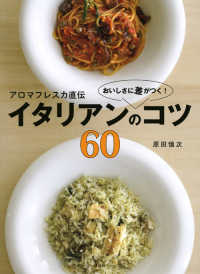出版社内容情報
日本の学校と教育が,世界から熱い視線を浴びている.だが,現状はどうか.過熱する受験競争,拡大する学校間格差,体罰やいじめの横行.学ぶ存在である人間の原点にたち返って教育を問い直すことが,いま切実に求められている.近代以降の学校の歴史をたどり,教育学の立場から,脱学校論など現代の学校批判にもこたえようとする.
内容説明
日本の学校と教育が、世界から熱い視線を浴びている。だが、現状はどうか。過熱する受験競争、拡大する学校間格差、体罰やいじめの横行。学ぶ存在である人間の原点にたち返って教育を問い直すことが、いま切実に求められている。近代以降の学校の歴史をたどり、教育学の立場から、脱学校論など現代の学校批判にもこたえようとする。
目次
1 教育とは何か学校とは何か(歴史の中の教育;教育とは何か)
2 学ぶことと教えること(学ぶことと子どもの発達;青年期の教育を考える―ある講演から)
著者等紹介
堀尾輝久[ホリオテルヒサ]
1933年福岡県に生まれる。1955年東京大学法学部卒。専攻は教育学・教育思想史。現在、中央大学教授、東京大学名誉教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
魚京童!
8
良き本でした。2013/12/19
かつお
7
前半は教育と学校の歴史で、まえに読んだ本と被るところが多かった。後半は学ぶこととは何かを考え、授業の実践がありわかりやすかった。学習と発達は二人三脚であり、片方が欠けていてはならないことがわかった。階段を登るのと同じで、学習することで発達し、発達することで新しいことを学習する。そして、学習の本質は発見。発見する喜びを子どもに感じてもらうと主体的に学習し、発達する。教師の役割は発見する喜びをもたらす授業をすることだと考えた。2016/04/09
トラちゃん
4
題名だけ見ると教育大学卒業間近の人間がこれを読んでいていいのか、という疑問がでるが、内容は結構難しく日本の教育のジレンマや問題点などが書かれていて、読者を考えさせる内容になっている。学ぶ喜び、自由に学問できるありがたさを今の若者は知らないといけないね(;´Д`A2012/02/17
ステビア
3
手堅くまとまってますな。2013/03/03
積杉
3
第一部は近代教育の歴史などが書かれていて、少々固いかもしれませんが、第二部は教員になりたい人はもちろん、多くの親にも読んでもらえれば良いと思います。事柄について発見の歴史までたどれば、必ず「難しい」と言われるような分野も生徒に納得して教えられるという意見は、私も仕事をしていて、とある中学の先生と同じ意見で合致しました。そのヒントが、この本では「微積分」の実例として書かれていますので、是非参考にして頂ければと思います。2012/08/28