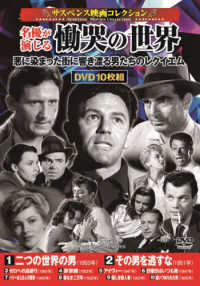出版社内容情報
経済学とはなにか,経済学の考え方とはどういうものか――日本を代表する経済学者が自らの研究体験を顧みながら,柔軟な精神と熱い心情をもって,平易明快に語る.アダム・スミス以来の経済学のさまざまな立場を現代に至るまで骨太いタッチで把え,今後の展望をも与える本書は,経済学のあるべき姿を考えるために格好の書物と言えよう.
内容説明
経済学とはなにか、経済学の考え方とはどういうものか―日本を代表する経済学者が自らの研究体験を顧みながら、柔軟な精神と熱い心情をもって、平易明快に語る。アダム・スミス以来の経済学のさまざまな立場を現代に至るまで骨太いタッチで把え、今後の展望をも与える本書は、経済学のあるべき姿を考えるために格好の書物と言えよう。
目次
1 経済学はどのうような性格をもった学問か
2 アダム・スミスの『国富論』
3 リカードからマルクスへ
4 近代経済学の誕生―ワルラスの一般均衡理論
5 ソースティン・ヴェブレン―新古典派理論の批判者
6 ケインズ経済学
7 戦後の経済学
8 ジョーン・ロビンソンの経済学
9 反ケインズ経済学の流行
10 現代経済学の展開
著者等紹介
宇沢弘文[ウザワヒロフミ]
1928年鳥取県に生まれる。1951年東京大学理学部数学科卒業。現在、日本学士院会員、東京大学名誉教授。専攻は経済学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
79
やはり何年たってもこの本はこの分野(新書などの解説書)では名著です。最近の動向が書かれていないということもありましょうが、それは最近の本に任せて、この本では経済学の基本的な古典といわれている経済学者あるいはその著書についての内容をわかりやすく解説しています。私は何年かに必ず読み返すことにしている本です。2015/08/16
樋口佳之
36
個別的な経済主体が、このような知識をもち、このような膨大な計算を瞬時的におこなうような能力をもっていたとすれば、市場制度そのものが成立し、機能する必然性はなくなってしまう。市場制度は、その構成員たちが、最終的な市場価格を事前に知ることができないときに、試行錯誤的におこなわれる取引を前提としてはじめて成立するものだから/難しいと感ずる部分、難しい上にそれを理解する事に意味があるのって疑問が先に立ってしまう2019/05/29
matsu04
23
日本を代表する経済学者・宇沢弘文が、そもそも経済学とはいかなる学問であるかを平易に語っており(とは言え、十分に難解であるが…)、新書版で安価に読めるのは嬉しい限りで、初学者にとっては必読の書と言えよう。1988(昭和63)年の執筆であるから、その後の激動の世界情勢は当然ながら反映されていないものの、現下の複雑な経済情勢を理解するためにも本書で基本を押さえておくことが大切だ。2015/08/26
呼戯人
18
アダム・スミスから始まり、リカード、マルサス、マルクス、ジョン・シュチュアート・ミル、そしてワルラスから始まる新古典派、そして新古典派への批判として宇沢が最も影響を受けたソースティン・ヴェブレン、ケインズ、ジョーンロビンソン、反ケインズの経済学まで手際のよい経済思想史。しかし、新書とはいえ内容は相当に難解だった。読むのに結構苦労した。しかし、経済学全体に対する宇沢の態度が明瞭に出ておりやはり名著だと感じた。ネオ・リベに対する批判・反論の鋭さに目を瞠った。2019/06/05
しんすけ
17
出版年月が気になる。奥付には1989/1/20と記されている。 ゴルバチョフのペレストロイカと反ケインズ派の矛盾露呈を後半に書き、著者がそれらに大いなる期待をかけていたことが判る。10か月後の1989年11月9日にベルリンの壁が崩壊したが、その後の東欧圏に自由が訪れることは無く貧困はさらに拡大している。反ケインズ派もその後は自由放任が経済学の根幹であるような主張を続けて、格差拡大を支援すらしている。宇沢弘文が「人間には理想社会を実現する能力がない」と晩年に書いていた。2020/02/14
-
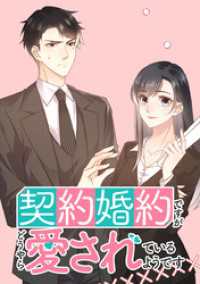
- 電子書籍
- 契約婚約ですがどうやら愛されているよう…