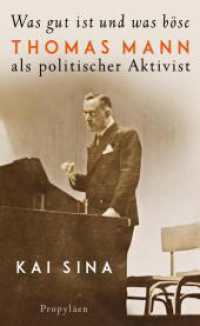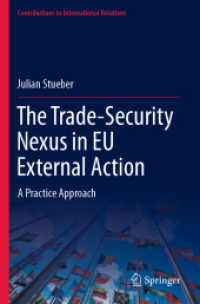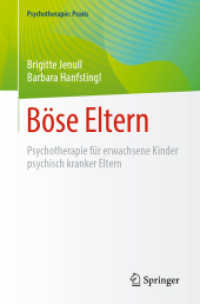出版社内容情報
一九八六年四月二六日,ソ連のチェルノブイリ原子力発電所で大惨事が発生! その六日後,米国の医師R.P.ゲイルはモスクワへ飛んだ.骨髄移植の世界的権威である彼は,ソ連の医師たちとともに,放射能をあびた人々の治療に当たる.その貴重な体験に,ソ連市民とのふれあい,ゴルバチョフとの会見をまじえ,「核」の恐怖を警告する.
内容説明
原子力発電所の事故以来、ゲイルはたびたびソ連を訪れる。謎の人物ハマーとともに行われた米政府首脳との会見。無人の町、チェルノブイリへの旅。心通わせた患者たちの相次ぐ死。彼を襲う、医師としての無力感。そして著者は、「核」時代を生きる私たちにできることを問いかけ、「みんな、チェルノブイリのそばに住んでいる」のだ、と結ぶ。
目次
第3部 続くモスクワへの旅(シュルツ国務長官との会見;チェルノブイリへ;医者として何ができたのか;再びチェルノブイリへ;チェルノブイリから学んだこと)
第4部 最後の警告(原子力発電への提言;核の時代に生きる)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
モリータ
14
◆訳者あとがきより;「だが、本書はそうしたもの(注:事故後の医療救援活動にいて医学的に専門的な立場から解明した報告)でなく、原発事故について一般の人々に警鐘を乱打したものである。ときには国際的な専門医としての視野から、体制上の制約でがんじがらめになり、先進的な医療器機が慢性的に不足しがちなソ連の医療体制のなかにあって、被爆者のため努力するロシア人医師の姿に焦点をあて、ときには一介の米国の市民として、ヒューマニズムの立場からソ連での体験や医療援助を赤裸々に語ったものだ。(p.222)」2022/03/08
カネコ
4
◎ チェルノブイリ原発事故に際して、急遽モスクワへ飛んだ骨髄移植の権威である米国人医師による医療活動の記録。当時(1986年)は米ソ冷戦の最中であり、両国の医師たちの協力行為がいかに異例の事態であったかを物語る。重篤な患者は次々に亡くなり、最先端の医療技術の無力と放射能の恐ろしさを見せつける。核兵器だけではなく「原子力がいかに死を招きやすいものであるか」を如実に示すドキュメント。放射能汚染には国境はなく、私たちが皆チェルノブイリの隣に住んでいることは、20年経過した現在も変わっていない。2009/06/13
NORI
2
チェルノブイリだけでなく、ソ連という国の情報も積極的に公開してきたゲイル博士だが、本書が古いせいか、下巻の後ろ3分の1くらいは、福島原発事故の後では、いささか古い内容になってしまった。いや、原発事故が起こる前に、読んでおけばよかったと思うほど皮肉なことになった。こんなに真剣に警告を発していたのに、なぜ、われわれ日本人は、原発を推進したのか? と思う内容だった。2011/05/30
青ポス
1
上巻に続けて読破。当時は米ソが核保有国として対峙している状態で、他国への核拡散は抑止しなければならないと書かれている。それから35年以上が経っているが、果たしてここに書かれている警鐘がどれほど実現しているだろうか。2025/04/14
taming_sfc
1
ゲイル、ハウザーによる1988年の訳書の下巻。クライマックスは「最後の警告」と題された第4部。ここで筆者らの原子力発電への提言がなされる。つまり、原発は上流から下流まで技術的に間違いがあってはならないが、人間はつねに間違う存在であり、ゆえに一つの事故が人類の存亡を決めるような災害もたらす原発をどのように扱うかは大変憂慮すべき問題である。 本来技術過信・人間の管理能力過信は、社会主義・共産主義に特有とされてきたが、この原発については体制に関わらず技術過信が蔓延している。その点を鋭く突く一冊。2011/03/15