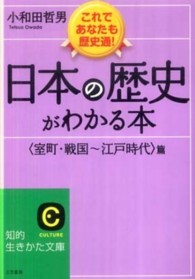出版社内容情報
十九世紀末以降,西洋古典音楽は調性の崩壊,民族的素材の見直しなどにより今世紀前半に多彩な発展をとげた.一九一○年代のバレエ音楽,二○―三○年代のオペラ,三○年代のバイオリン協奏曲など各時期の代表的作品の検討を通して,歴史の激動とともに音楽がどのように変容していったのかを明らかにし,戦後音楽への影響を考える.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
乙郎さん
5
19世紀後半からの現代史と並行して語られる音楽の歴史。多層的な聴き方に導いてくれるようで、非常に面白かった。ドビュッシーの異国趣味に惹かれる。2024/01/28
PapaShinya
3
この本は名著だと思います。是非”現代音楽は怖くない―マーラーからメシアンまで”と併せて読みたい。ガーシュウィンも含んでいますが、ほぼクラシック音楽の現代史です。で、その中でも”現代音楽”と呼ばれる調性感のない、あるいは調性感の薄い音楽を書いた作曲家の作品とそれを取り巻く政治状況が詳しく書かれている。ヒンデミット事件が特に面白い。フルトヴェングラーの政治音痴ぶりも。そういう個々の記述だけでなく、現代音楽という大きな流れが何故ナチスやスターリンに毛嫌いされたか、そして今の状況がどういうことなのかがわかります。2023/07/16
横丁の隠居
2
1986年の出版だが、今読んでも十分面白い。20世紀初頭の音楽を当時の政治状況を絡めて叙述するという、ロスの「20世紀を語る音楽」の序章といってもいい。つくづく、音楽は時代を離れては存在し得ないと思わされる。2019/06/15
丰
0
Y-202006/12/20