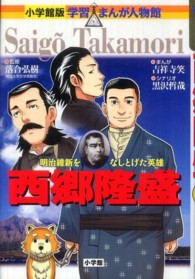出版社内容情報
白エプロンにたすきがけ,やかんを下げ,あるいは小旗をふって出征兵士の見送りに,帰還兵士の出迎えにくり出した婦人たち.昭和七年,わずか四十人で発足した一つの組織が十年後には一千万にふくれ上り,日中戦争下の銃後体制を支える要の一つとなる.国防婦人会の活動に焦点を合わせて,民衆動員の様相を鮮やかに描く銃後の社会史.
内容説明
白エプロンにたすきがけ、やかんを下げ、あるいは小旗をふって出征兵士の見送りに、帰還兵士の出迎えにくり出した婦人たち。昭和七年、わずか四十人で発足した一つの組織が十年後には一千万にふくれ上り、日中戦争下の銃後体制を支える要の一つとなる。国防婦人会の活動に焦点を合わせて、民衆動員の様相を鮮やかに描く銃後の社会史。
目次
1 献金現象と軍拡―「満州事変」
2 カッポウ着台所を出る―国防婦人会現象
3 なぜ国防婦人会なのか―非常時の視点
4 軍事か生活か権利か―日常の視点
5 原点にて―別れと見送り―日中全面戦争
6 銃後と生活―国民精神総動員から隣組へ
著者等紹介
藤井忠俊[フジイタダトシ]
1931年山口市に生まれる。1955年早稲田大学法学部卒業。専攻は日本近現代史・民衆史。「季刊現代史」創刊以後、現代史の会主宰、大学教員など。駿河台大学講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おかむら
36
朝ドラで戦争中になるとよく出るかっぽう着にタスキかけたイヂワルなおばちゃん達。あの人らは何者? 日中戦争下に会員1千万を集めた女性組織 国防婦人会の発生から終焉までの紆余曲折。善意で始まった活動が国(軍部)に利用される、とも言い切れない庶民と戦争の関係がとても興味深い本。善意と言ってもあの時代のは「お国の為」ってのが怖いとこ。右傾化だの戦前回帰だの言われてる今ですが、マジで回帰したいのか安倍は?安倍はしょうがないとしても保守系女性議員の方はどうかしてるぜ、としか思えんわ。(発行1985年で閉架書庫本)2016/07/16
kenitirokikuti
9
図書館にて。木下惠介監督映画『二十四の瞳』の出征見送りシーンにはタスキにカッポウ着の国防婦人会が描かれているが、史実では大日本婦人会に統合後である。反対に映画『陸軍』(1944)では組織前。イメージなのである▲国防婦人会は、別れと見送りの社会学・民俗学である。『鬼滅の刃 無限列車編』受容の大きなヒントとなった。▲別のメモ→ https://bookmeter.com/mutters/2301650222021/10/13
Eiki Natori
8
NHKのドキュメンタリーでも紹介された国防婦人会。元々は出征兵士の見送りをするために作られた小さな組織であるが、組織が大きくなるにつれ、軍部によって利用される。 政治的な意図がないかっぽう着だからこそ、入会者が増え、「善意」で戦争に加担していく。そしてそれがやがて全体主義につながっていくのだが、どうして全体主義が生産されるのかという一つの例としての歴史的事象を学ぶことができる一冊ではないのか。2021/09/21
にゃん吉
6
官庁や軍部といった上の側の思惑、国民の側のメンタリティーといった視点から、国防婦人会の誕生、発展、消滅までの経過が叙述されています。あとがきによれば、それまであまり注目されていなかった分野の研究の端緒となる一冊のようです。国防婦人会との比較等から、愛国婦人会、全関西婦人連合会、婦選獲得同盟、大日本婦人会等々、戦前の婦人団体についても広く触れらていますが、元々全然知らない分野だったので、途中で団体の名称を混同しそうになったりしながら、どうにか読了しました。 2021/12/27
デューク
4
「戦場に100万人の兵士を、銃後に1000万人の婦人を動員したこと、これが日中戦争に際しての民衆動員の実像であった」。そう語る筆者による、銃後形成の歴史。カッポウ着に白たすきで出征兵士を見送る婦人の一団。戦争映画で必ずと言っていいほど描かれる光景である。彼女らが所属していたのが、「国防婦人会」という民間組織。似たような性格の、愛国婦人会や連合婦人会との三つ巴の勢力争いを制し、覇権を握るに至った理由はどこにあるのか。もう一つの15年戦争史であり、組織マーケティング論としても読める一冊。おすすめ2016/08/24
-

- 電子書籍
- 31番目のお妃様【タテスク】 Chap…
-

- 電子書籍
- RIDERS CLUB No.166 …