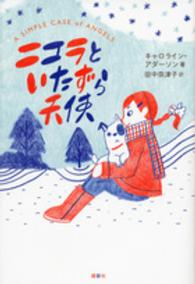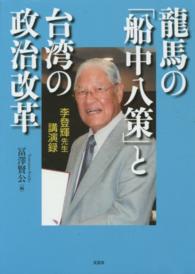出版社内容情報
いまヨーロッパではどんな言語がどれくらいの数の人びとに話されているのだろうか.そして,どの言語が増えており,また減りつつあるか.その原因は何か.一億を超す話し手をもつロシア語から,一旦は滅びながら再生への懸命な努力がつづけられているマンクス・ゲーリク語やコンウォール語まで,ヨーロッパ諸言語の問題状況を描き出す.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てり
1
第1部で直前に読んだメイエを批判的に取り上げていてとても面白く読めた。なんというか、フランス語にこだわるフランス人のアクの強さが印象的。第2部のヨーロッパで話される67言語の総覧も興味深く読めた。Youtubeで各国の話者の発音を聞くのも楽しい。2023/03/05
misui
1
「言語=民族」というイデオロギーをめぐる現代ヨーロッパの言語状況と諸言語概観。文章語の獲得が近代国家形成の前提条件だったとか俗語の解放とか、言語がアイデンティティを証することのメリット・デメリットを押さえる感じで。2011/05/11
穀雨
0
かなり古い本だが、その系統や書き言葉としての歴史が言語別に書かれていて分かりやすい
xzelph
0
前半部分はそれなりに興味深い概説。ただし社会言語学というよりはむしろ言語政策の分野だと思った。後半部分ははっきり言って信用できないので、興味を持ったら裏取りが必要。個人的に自信を持って詳しい間違いが指摘できる箇所は例えば以下の通り。キュリロス・メトディオスが作った文字はキリル文字ではなくグラゴール文字(92頁)。ラトヴィア語は単純な第一音節アクセントの言語ではなく、強勢とは別に長母音と二重母音に音調がある。また、ラトヴィア語が接触したのはフィンランド語ではなくリーブ語(Livonian)(152頁)。2020/09/18
もす
0
第1章は言語そのものについて論じています。言語のいわゆる純化政策(その言語を外部言語から守ろうとする動き)の他、ラテン語から英仏独の言語に知識人達の言葉は代わるのだろうかということについて書いてあり、非常に面白い内容でした。やはり1985年発行らしさがありますね、ソ連のこともよく書いてあり、そこもまた興味深かったです。2020/04/03