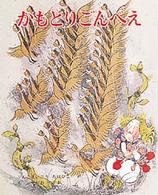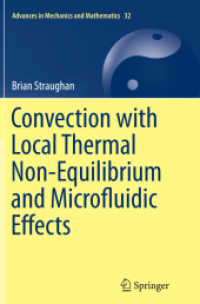出版社内容情報
現代の文化的創造は,歴史の真実に正しく立脚することによってはじめて可能となる.著者は,原始いらいの日本の文化の流れを,その担い手,文化的伝統の形成過程,海外の文化との交流などの視点からとらえ,その中から私たちが二一世紀に向けて真に継承すべきものを明らかにする.英訳されて海外にも広く紹介された旧著の全面改訂版.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
31
古代から近世までの文化史。図版が多く、読んでいて飽きない。著者独自の視点が加わることで、単なる古事の羅列ではなくしているのもよかった。2014/12/22
moonanddai
13
初版に続き再読。作者も認めるように、何をもって文化とするかは、難しいところ。それでも通史・概説ということにすれば、律令文化とか貴族文化、武家文化、町人文化といった社会的中心階層のいわゆる「時代精神」みたいなものや、財のヴォリューム的所在階層中心の記述とせざるを得ないのでしょう。ただ、例えば中世以降、農村・漁村の住民(網野氏的に言えば「百姓」)が流通、商取引に相当関わっていたとすれば、本書で言う「一方的被搾取」階層で見るべき文化は少ないとするのも、(今だから言うのですが)幾分見直しがいるのかもしれません。2025/07/08
Hidetada Harada
11
学生時代は単純に覚えるべき対象だった文化史上の偉人、名作、イベントの歴史的な意味、お互いの関係性が知りたくて手に取った本。めちゃくちゃたくさんの気づきの中、いちばん響いたのは家父長制が江戸時代以降の慣わしだということ。それも時の為政者の都合のためとは。歴史を学ぶ大切さを感じた読書でした。2023/04/28
半木 糺
7
戦後の日本文化・思想史の大家であった家永三郎の代表的著作の一つ。家永自身が左に大きく傾いていたため、現在見るとかなり偏った表記が目立つ。例えば明治期の指導者を「近代的な政治思想や社会思想を排斥した」と断罪し、「民衆」の下からの力を過大評価するあまり、社会上層部の文化を「実態から遊離した退廃的文化」と断ずるなどの記述も散見される。ただ序文の「日本の文化的伝統はそれが価値あるものであるならば、必ず人類文化の発展のために、なんらかの寄与をなすであろうし、またなさしめなければならない」との文言はまさに金言である。2014/03/02
白義
7
今では家永裁判の印象ばかりが強いけど、さすがにこういう通史を見るとやっぱり凄い学者だったんだなあと思う。いわゆる反皇国史観で今だと単純かつ古いかもしれないが、トータルな日本文化、芸者、思想の歴史をこれだけ安定した形でまとめているのはお見事としか言いようがない。古代から近代まで大方の流れがイメージできる。近世文化の生命力を特に感じる。なんだかんだで一回は読んどくといい本2012/02/26