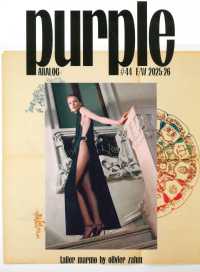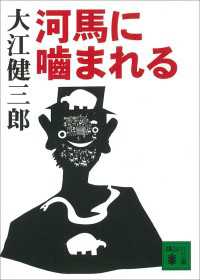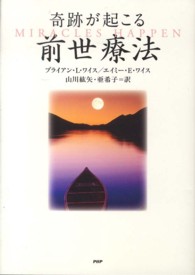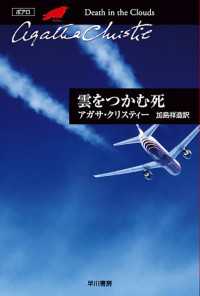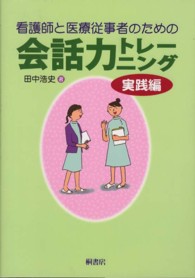出版社内容情報
江戸時代に日本の出版業の出発点となった京都と,近代以後その集中の規模と総合性において世界でも比類のない巨大な書物同業者街となった神田.愛書家として知られる著者は,厖大な文献を探査し,多くの聞き書きを行なって,この東西二都の書肆街(本屋街)の経営史を描きだした.『図書』連載中から好評をもって迎えられた.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
コットン
64
京都と東京は神保町の昔から昭和までの変遷が語られている。昔は東京より京都のほうが本屋が多かったとは意外な気がしたが、考えてみると寺や大学も多いのでわかるような気がする。2023/06/27
緋莢
13
この本の存在を知ったのは、新潮新書の創刊ラインナップの一つ坪内祐三『新書百冊』。それから少しして、古書店で購入したので20年くらい積読にしていました。で、買った時ですら、この本は刊行から年数が経っているなぁ、と思っていたのですが調べたら、何と1979年刊行でした。そのタイトル通り、東西の書肆街(本屋街)の歴史について書いた本。東は勿論、神田神保町。西は江戸時代に出版業の出発点となった京都(続く 2024/01/13
たか
11
神保町、京都の古書店の時代変遷について詳しく解説してある。古いから字が多くてちょっと読みにくい。2015/05/19
スズツキ
4
出版社や書店の歴史を江戸時代まで遡って詳しく解説していますが、実在のものが詳しく地図付きで掲載されていてもそれは土地勘のない人間が見ないとあまりピンとこないような。2017/03/21
mft
3
京都と神田がテーマ。京都は主に江戸時代で、神保町は明治・大正期が中心となる。1979年の本なので昭和半ば(東販日販以外に中小取次が神保町にいくつもあったころ)まで。「神田神保町書肆街考」と重なるところもあるが、華族の誰それがというような話はこちらの方が多い(○○子とあるのが○○子爵の略だと最初解らなかった)2025/04/21