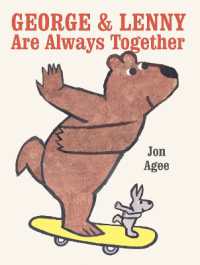出版社内容情報
十三世紀初頭ジンギスカンが樹立したモンゴール帝国の版図は,遠く東欧から南ロシアにまで及んだ.その末裔とおぼしき蒙古族の一部がアフガニスタン奥地のどこかにいる――.この地図にも記録にも残されていない民族を探し求めて,遂にこれをつきとめ,その風習,言語を調査した京大カラコルム・ヒンズークシ探検隊人類学班の貴重な記録.
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マッピー
14
モゴール族。アフガニスタンのモンゴル族のことを、現地の呼び方に従ってモゴール族とよんでいるそうだ。アフガニスタンではモゴール族は少数なので、彼らの住んでいる地域を探すのも難しかったが、モゴール語(アフガンなまりのモンゴル語)を話す人が、既にほとんどいなくなっていて、言葉の収集が本当に大変そうだった。言葉は生きているとよく言うけれど、話す人がいなくなってしまえば、言葉は簡単に失われてしまうのだ。かろうじて単語の意味は分かるけれど、文章は話せない人すら、ようやくに探し当てたのだった。言葉、大切にしないとな。2024/02/22
アメヲトコ
7
1956年刊。京大探検隊の一員として、消滅危機語であるモゴール語を求めてアフガニスタン(当時はまだ王国!)のゴラート高原を訪ね歩く調査行記。『バーブル・ナーマ』で「モグール族」がしばしば登場したことを思い出しますが、かつてのモンゴル遊牧民の末裔がアフガンの奥地で細々と農業に従事し、遊牧民のパシトゥーン族に圧迫されているというのは諸行無常感あります。建前と本音を政治的に使い分けるふるまいの機微についての鋭い分析は、敗戦国民だから分かることと言いますが、氏が生粋の京都人だからというのが大きいような気がします。2024/12/20
まふ
7
京都大学カラコルム探検隊のメンバーとしてアフガニスタンの奥地にモンゴル族の末裔であるモゴール語を話すモゴール族を探しに行った探検記。京都大学的「なんでも体験」的精神であえて困難に突き進む精神が、この書にも表れている。面白い。多分この辺であろうと探っていくが期待外れの連続。梅棹忠夫はもともと山男であるからこのような臭い、暑い、体力消耗的環境に突入して成果を上げるのだということが実感できる本であった。2020/03/03
シュークリーム・ヤンキー
7
古本屋でたまたま出会った一冊。ひじょうに読みやすい文章。 この本の出版は、あのレヴィ=ストロースが『悲しき熱帯』を出したのとほぼ同じ時期だ。戦後の貧しかった時代に、こんな冒険をして記録を残した日本人がいたということに、まず驚いた。そして他民族の関係に入り込んで研究調査をすることの緊張感や、科学と宗教の関係性に関する考察(pp104)は、70年以上が経った今でも古さを感じない。 恥ずかしながら梅棹氏を存じ上げなかったが、ほかの著書も読んでみたいと思った。2019/04/11
穀雨
6
1955年、アフガニスタン(当時は王国)にモンゴル帝国の末裔とされる民族を追った探検記。ひらがなの多いエッセイ風の筆致でとにかく読みやすいが、現地民を蔑むような表現が時折顔を出すのは時代も時代で仕方のないところか。一読して、モゴール族の村々がいまどうなっているのかがただ気になった。2024/10/25
-

- 和書
- 固有名詞英語発音辞典