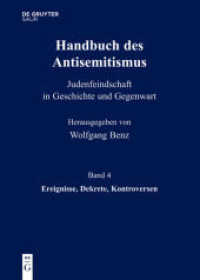出版社内容情報
著者は,偶然の運命からメキシコに落ち着き,国立野外美術学校教師に迎えられ,革命後の生気に満ちたメキシコ・ルネサンスの十数年間を子供の絵の指導にあたり,大人の猿まねでない,自由な創造的な児童画を育てあげた.当時の興味深い体験の記録をまとめた本書は,児童美術教育に大きな示唆を与えるだろう.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Anna Shibata
3
まるで上等な私小説のような本だった。本職の作家さんではないので、ところどころ、ん?となる部分もあるのだけれど、全体に力があるので読めてしまう。子どもが自ら成長しようとする力(著者は"自由を希求する力"と表現)を信じて、大人は、余計な手出しや矯正をしたり、先回りして答えを与えてしまったりしないほうが、子どもは真っ直ぐ育つ。といった主旨が読み取れた。これには同感。この本は戦前のモノだけれど、現代でも、日本の教育は矯正の色が濃いし、そうでなければ甘やかし過ぎで、「子どもに任せる」という部分が少ないと感じる。2017/08/03
sk
2
自由な創造力2025/08/17
8
0
メキシコ時代の児童絵画教育の回想。画家なのに自分の絵の話はほとんどないのが特徴的で、筆致も視点もまさに教育者である。世田美で絵画展を見てきた後だけに、あれだけ“自分の絵”がある筆者の絵画教育に、“自分の絵”が出てこないことに驚愕。 フロイトを読み込んだヒトが考える、児童が絵画で表現する深層心理と、その発露としての児童絵画。小学校の美術の授業っていうのは、こうあるべきだったんじゃないかと思ったけど、汲み取れる教師がいなさそう。2024/10/12
オオタコウイチロウ
0
おもしろかった。百年前の話である。究極のところ、絵画=非概念、文字=概念である。前者の特質に根差した、教育の二面性のうちの一側面をうまく活用、あるいは見出した過程のルポルタージュ。2024/06/07