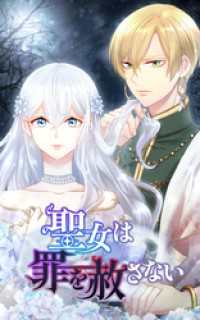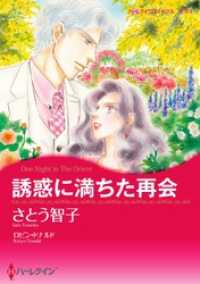出版社内容情報
光源氏の青春の出発を語る「桐壺」を初巻として,源氏物語五四巻は成り立っている.著者は,この作品の顕著な特徴が,物語の成立していく過程によって主題・方法が発展していくところにあることを指摘し,そうした視角から,物語の全貌とその本質を,作者紫式部の内面的な生活とのかかわりにおいて生きいきととらえる.
内容説明
光源氏の青春の出発を語る「桐壺」を初巻として、源氏物語五四巻は成り立っている。著者は、この作品の顕著な特徴が、物語の成立していく過程によって主題・方法が発展していくところにあることを指摘し、そうした視角から、物語の全貌とその本質を、作者紫式部の内面的な生活とのかかわりにおいて生きいきととらえる。
目次
1 光源氏像の誕生
2 いわゆる成立論をめぐって
3 宿世のうらおもて
4 権勢家光源氏とその周囲
5 別伝の巻々の世界
6 紫式部と源氏物語
7 「若菜」巻の世界と方法
8 光源氏的世界の終焉
9 結婚拒否の倫理
10 死と救済
著者等紹介
秋山虔[アキヤマケン]
1924‐2015年。1947年東京大学文学部国文学科卒業。東京大学名誉教授。専攻は日本古代文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かもめ通信
19
1924年生まれの著者が1968年に刊行したという少々古い本ではあるが、Kindle Unlimitedで読むことが出来るというので、軽い気持ちで読み始めた。 自身の「読み方」を強力に打ち出すのではなく、様々な学説を紹介しつつ、「源氏物語」本編とその周辺を掘り下げていく形の筆運び。 “当時の読者は光源氏のモデルとして誰を思い浮かべたか”とか、“「帚木」当時の光源氏が17歳と推定される根拠”などという話あたりまでは、ふむふむと読み流していたのだが、いわゆる「成立論」をとりあげる辺りから、がっつり前のめりに。2024/02/26
1.3manen
12
光源氏18歳で瘧(わらわ)病(31頁)。広辞苑によると、おこり というらしく、間欠熱、マラリアとのこと。蚊に刺されたのかな? 「絵合」で光源氏は世の無常、出家の念願を語っているという(59頁)。学識ぶることのみにくさをもっとも敏感に感じとっていた紫式部(96頁)。偉ぶりたいのを戒められる。式部の家系図(98頁)では、文事に生きるお家柄ではあったようだ。実生活に生きることに絶望した式部(212頁)。虚構でも生きられぬ世界だというのは酷なものだ。孤絶したきびしさ、そして、無限の悲しさであるという。厭世、悲愴。2013/07/30
はちめ
10
再読だが更に新鮮だった。今回は、著者が指摘している紫式部が登場人物の女性たちに託した思いという点での読みが深まったと思う。特に宇治十帖の大君がなぜ頑なに薫の求婚を断るのか、なぜ浮舟は出家せざるを得ないのかといった疑問について、紫式部が当時の女性の生き方としてそう書かざるを得なかったということが說明されている。紫式部は自身は受領階級の娘に過ぎなかったが、たまたまその文才により宮中に採り入れられ、藤原道長を中心とする権力闘争の中での女性たちの生き様も直接目にしていた。その中での女性の生き様を描いた。☆☆☆☆☆2021/12/29
はちめ
10
1968年出版。手元の本は1972年版、本箱の奥に発見したので読んでみた。岩波新書が180円とかの定額だった頃の本だ。確か半透明のセロハン紙のようなもので覆われていたのではなかったか? 本は古いが内容的には新鮮だった。粗筋と共に登場人物達の心情、そしてその向こうにある現実社会を生きる作者である紫式部の思いも判りやすく書かれている。現代語訳で一読した後に読んだ方が良いが、源氏物語に興味を持つための1冊としても役立つと思う。☆☆☆☆★2019/05/09
ヒロミ
8
すごく昔に書かれた本なので(昭和44年初版)表現が古めかしくフォントも小さく正直目が慣れるまで時間がかかりましたが、ベーシックな源氏物語論として面白く読みました。最近「若菜」及び第二部熱が高まっているので若菜のことを書いた章は興味深かったです。源氏物語という古典は本当に魅力的な仕掛けがたくさんだなあと思います。2013/05/31