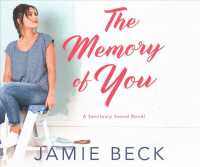内容説明
著者は十九歳のとき印度に渡り、一年有余の苦心の結果チベットに入国し、外国人として初めて許されてラマ教団の僧院に入り、十年間ラマ教の研究に没頭した。本書は著者が親しく見聞したチベットの地理風俗政情について叙述したものである。チベットの人文も政治組織も、またその自然すらもラマ教と不可分の関係に存することを説いている。
目次
第1章 ラマ教概觀(ラマとは何か;ラマの教團 ほか)
第2章 西藏の自然と人文(西藏の名稱;西藏の自然 ほか)
第3章 西藏の政府と政治(ポタラ宮殿;行政機構 ほか)
第4章 ラマ教の歴史(ラマ教を中心とせる西藏の歴史;ダライラマ十三世の日常 ほか)
著者等紹介
多田等観[タダトウカン]
1890‐1967年。秋田県生まれ。僧侶、仏教学者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
49
1942年初刷、2018年復刊第5刷。若き日にチベットに入り、先代のダライラマ13世から知遇を得て10年間修行した著者が、1世紀昔の、仏教を中心にチベットの文化・慣習・政治を述べる。古い文章は最初は難しく思えるが、読み進めていくうちに、時代も場所も、日本の日常からはるかに遠い宗教国のエキゾチックさを、身近に感じられるようになる。著者は『チベット滞在記』という本も残しており、講談社学芸文庫に収録されているらしい。そちらも読んでみたい。 2019/03/10
nagoyan
13
優。昭和17年刊。著者の多田等観は、大正2年入蔵。大正12年に帰朝するまで10年間チベットに滞在。1920年にダライラマ十三世から受戒。本書は、ラマ教(チベット仏教)に多くの頁数が割かれるも、当時のチベットの国政、風俗、人情等網羅的にチベットを紹介(第1章ラマ教概観、第2章西蔵の自然と人文、第3章西蔵の政府と政治、第4章ラマ教の歴史)。嘗て剽悍で知られた西蔵人も、当時は軍事力は皆無に等しく、英、露、「支」に翻弄された歴史も簡単にではあるが、触れられている。「文明」というものの野蛮さを思う。2021/12/21
多目的トマソン
3
教科書的にチベットの概説をするのではなく、当時の生の雰囲気を語っているところが興味深かった。 外交関係を当時の国民感情に触れながら紹介したり、ダライ・ラマ13世の人柄を伝えたり、チベット人の鼻のかみ方が不潔だと忌憚なく断じたり。2019/04/15
-
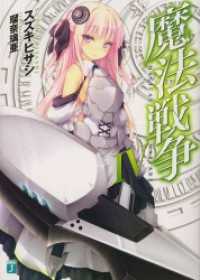
- 電子書籍
- 魔法戦争 IV MF文庫J