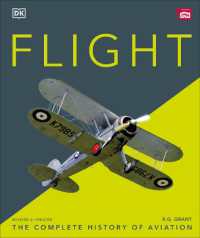出版社内容情報
インドにおける零の発見は,人類文化史上に巨大な一歩をしるしたものといえる.その事実および背景から説き起こし,エジプト,ギリシャ,ローマなどにおける数を書き表わすためのさまざまな工夫,ソロバンや計算尺の意義にもふれながら,数学と計算法の発達の跡をきわめて平明に語った,数の世界への楽しい道案内書.
内容説明
インドにおけるゼロの発見は、人類文化史上に巨大な一歩をしるしたものといえる。その事実および背景から説き起こし、エジプト、ギリシァ、ローマなどにおける数を書き表わすためのさまざまな工夫、ソロバンや計算尺の意義にもふれながら、数字と計算法の発達の跡をきわめて平明に語った、数の世界への楽しい道案内書。
目次
零の発見―アラビア数字の由来
直線を切る―連続の問題
著者等紹介
吉田洋一[ヨシダヨウイチ]
1898‐1989年。1923年東京大学理学部数学科卒業。専攻は数学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
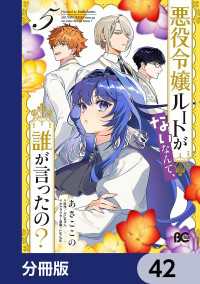
- 電子書籍
- 悪役令嬢ルートがないなんて、誰が言った…
-

- 電子書籍
- 麻衣の虫ぐらし【分冊版】20 バンブー…