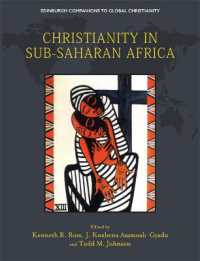出版社内容情報
第二部の第六~九巻を収録。諸大陸の様々な気候帯と民族文化の関連を俯瞰した後、人間に内在する有機的力を軸に、知性や幸福について考察する。カントとは一線を画し、人種概念を否定して人類の多様性を求めたヘルダーの、独特な自然観・人間観が展開される。(全五冊)
内容説明
第二部の第六‐九巻を収録。諸大陸の様々な気候帯と民族文化の関連を俯瞰した後、人間に内在する有機的力を軸に、知性や幸福について考察する。カントとは一線を画し、人種概念を否定して人類の多様性を求めたヘルダーの、独特な自然観・人間観が展開される。
目次
第6巻(北極周辺の諸民族の有機組織;地球の背であるアジア周辺の諸民族の有機組織 ほか)
第7巻(人類はかくも多種多様な形で地球上にその姿を現しているが、どこにおいても一つの同じ人類である;一つの人類は地球上のいたるところで風土化されてきた ほか)
第8巻(人間の感覚は形態や風土とともに変化する。しかしいたるところで人間による感覚の使用はフマニテートに至るものである;人間の想像力はいたるところで有機組織と風土に即している。しかしそれはいたるところで伝承によって導かれている ほか)
第9巻(人間はとかくすべてを自分自身から産み出すと思い込んでいるが、自己の能力の発展においては他のものに左右されるところがきわめて大きい;人間形成の特別の手段は言語である ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
加納恭史
13
さて、シェイクスピアに傾倒しつつ、今回ヘルダーのこの本「人類歴史哲学考(二)」をゆったり読む。やや冗長であり、この二巻は風土から人類を読み解くわけだ。人間は風土の中の自然から民族誌に入る。地理的歴史は、北極圏、アジア、アフリカ、熱帯、アメリカの緒民族について考察する。先進国と未開の区分でなく、人類の多様性を考察する。ヘルダーは色彩の多様性についてはゲーテの「色彩論」と同じ地平に立つ。彼はフマニテート(人間性)を理性のみならず感情、感覚など有機体として捉える。彼は最初はカントに師事したが次第に反発した。2024/08/13