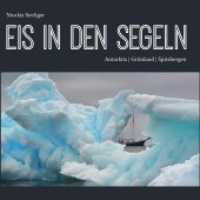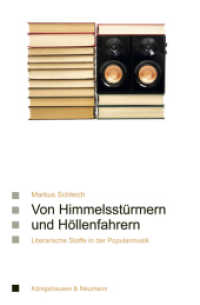出版社内容情報
1945年8月のポツダム宣言受諾は、天皇主権から国民主権への革命であった――日本の憲法学を牽引した宮沢俊義(1899-1976)は「八月革命」説を唱えて、新憲法制定の正当性を主張した。その記念碑的論文をはじめ、主権の所在をめぐる尾高朝雄との論争時の論考、現在の通説の淵源となった論文「国民代表の概念」等を収録。
内容説明
1945年8月のポツダム宣言受諾は、天皇主権から国民主権への革命であった―。日本の憲法学を牽引した宮沢俊義(1899‐1976)は、「八月革命」説を唱えて、新憲法制定の正当性を主張した。その記念碑的論文をはじめ、主権の所在をめぐる尾高朝雄との論争時の論考、現在の通説の淵源となった論文「国民代表の概念」等を収録する。
目次
八月革命と国民主権主義
日本国憲法生誕の法理
国民主権と天皇制とについてのおぼえがき―尾高教授の理論をめぐって
ノモスの主権とソフィスト―ふたたび尾高教授の理論をめぐって
憲法改正案に関する政府に対する質疑
国民代表の概念
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
またの名
8
天皇主権マンセーな大日本帝国憲法の枠内では国民主権への正規手続きによる移行は論理的に不可能なので、45年8月に戦争降伏を受け入れた瞬間に事実上の革命が発生し体制転覆したと説く論文。すべて国法は憲法的限界を超えることが許されず、仏憲法なら共和制を廃する改正を禁じ米憲法において国民主権を否定する改憲は不許可という点を踏まえ、その限界をぶち破り誕生した日本国憲法の成立根拠を探る。多様な議論が盛んだった改正前後、国民主権ではなく国家主権も唱えられたが具体的に誰が主体なのか述べない意味不明理論として珍説扱いで撃沈。2025/08/15
nagoyan
6
優。長谷部の解説は鋭い。どこかでも書かれていたかもしれないが、清宮らの通説的憲法論における根本規範とケルゼンの根本規範のずれを指摘する。それが、フッサール流根本基本と接続するというねじれ。まだまだ、未消化だが、とにかく刺激的。2025/09/12
Hiroshi
5
八月革命説とは、日本国憲法(新憲法)の制定は大日本帝国憲法(旧憲法)の憲法改正手続きによったのであるが、その制定に瑕疵がなかったことを説明する理論である。この説は丸山眞男が唱えたのであるが、丸山の許諾をえて著者が論文とした。新憲法(国民主権主義)と旧憲法(君主主権主義)は性格が異なる。旧憲法と性格が異なる新憲法を旧憲法の改正手続きで制定できるのかが問題となる。自らの憲法を自殺させるよう権限を憲法が与える筈がないからである。憲法の改正手続きには限界があるのだ。この説はポツダム宣の受諾時に革命があったとする。2025/12/07
葉月
5
面白かった。いわゆる八月革命説を唱えた日本法学の大家による論文集+α。八月革命説は右派、左派双方が好んで話題にし攻撃/利用する印象があり、特に戦前と戦後の連続性を論じる際に引き合いに出されやすいが、この論文で問題となっているのは日本国憲法の手続き上の正当性である。憲法改正限界説(憲法改正ではその憲法の根本となる理念を改めることはできない)の立場にいた宮沢としては、神権的な天皇の統治権に基づいて設計された大日本帝国憲法が、改正という手続きで国民主権を謳う憲法へと生まれ変わるのは容認できぬ事態だった。2025/06/19
令和の殉教者
2
旧憲法は天皇主権を謳い、それが新憲法では国民主権に改められた。この変容はいかに説明されるか。著者は、主権者の交代は憲法の自己否定となるため、(実際にはその手続きが踏まれたにもかかわらず)その改正限界を超えているという。それでもなお国民主権憲法が生じたのは制定以前に実態として日本が国民主権国家に変化していたからだ。筆者はその転換点をポツダム宣言の受諾に見出し、この体制変化を「(八月)革命」と呼んだ。新憲法下でも天皇制は残ったが、主権者としての天皇から国民に支えられての天皇へと意味を大きく変えることとなった。2025/08/17
-

- DVD
- 格闘家 総合格闘技編