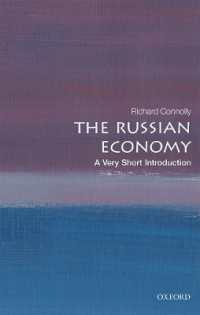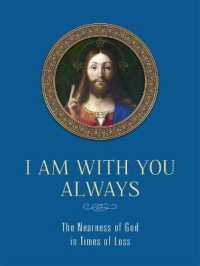出版社内容情報
マルクス経済学を構築した宇野弘蔵(1897- 1977)の代表的著作.資本主義の基本原理を解明することで独自の宇野理論を表明している.
内容説明
宇野弘蔵(1897‐1977)は、マルクスの『資本論』を、精確にかつ批判的に読むことで社会科学としての独自のマルクス経済学を構築した。本書は、宇野理論の基礎を集約的に述べた代表作。『資本論』への望みうる最良の手引書であると同時に、いまだマルクス経済学への根本的な問題提起を喚起し続けている著作である。
目次
第1篇 流通論(商品;貨幣;資本)
第2篇 生産論(資本の生産過程;資本の流通過程;資本の再生産過程)
第3篇 分配論(利潤;地代;利子)
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かわうそ
50
原書『資本論』と少し格闘してから本書に臨んだ方がいいのかなと思いました。 マルクスからイデオロギー的な要素を抜き取り、『資本論』を純化しようとした男がこの本の筆者である宇野弘蔵です。 近代経済学では今ある息苦しさ、資本主義の根本というのは全く解明できません。 そもそも近代経済学とマルクス経済学では目的からして違う訳です。近代経済学は資本主義社会を円滑に動かすためにあるのであってマルクス経済学のように資本主義社会を解明しようとする学問ではないのでどちらが優れているかという問題は問う必要がないです。2023/09/10
1.3manen
39
1文が長過ぎるのが難点。経済学は、商品経済に特有なる諸現象を解明するものとして発達してきた学問(9頁)。経済学は、資本主義下では、生産力の異常発展、その社会的影響を解明し、社会主義社会にも共通する経済生活の一般規定を明らかにする(11頁~)。経済学は、資本家、労働者、土地所有者との純粋資本主義社会を想定し、そこに資本家家的商品経済を支配する法則を、その特有なる機構と共に明らかにする経済学の原理が展開される(経済原論20頁)。2016/04/04
ビイーン
38
佐藤優氏が薦めているため読んでみた。正直、難しくてわからない。本書は学生運動で荒れた1970年代に大学生が持ち歩く知性のシンボルの一つだったらしい。日経平均株価が1989年末バブル期の高値超えというのに、私はお給料が増えなく脱デフレを実感できていない。そんな社会の矛盾が変わらない限り、難解で理解できなくともマルクスを読む事は止められないだろう。 2024/02/24
kaizen@名古屋de朝活読書会
26
イギリスの古典的経済学の流れを組む学問体系。 ケインズらの近代経済学と対比して、原理に強いが、 現状分析に偏りがあるのが難点であると考えている。 本書は原理の部分なので、本書を読んだだけでは、 現状分析にどのように有効かは分からないかもしれない。 自分の経験をうまく表現できるようであれば、有用な道具となるだろう。 近代経済学が現状の説明に偏りすぎて、 現状を肯定的に描写するのに力を入れているのは、 古典経済学の反動なのかもしれない。 2026/01/30
きゃれら
23
マルクス資本論には経済書として「それはどうなの?」という突っ込みどころが僕のような素人にもいくつかあったが、そうした論点を、資本論に修正を求める形でコンパクトにまとめた本。資本論そのものは論理が入り組んでいてとんでもなく読みにくいのだけど、こちらは論理が充実してあまりにも濃厚で、読んでいて息が抜けずすごく時間がかかった。しかしながら、資本主義を資本論の立場から理解するのに適切なガイドブックではないか。資本を会社に読み替えれば、経営者も目を通すべき論考がされていると思った。2022/01/08
-

- 洋書
- DE LA MAGIE