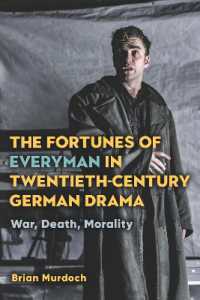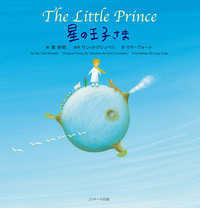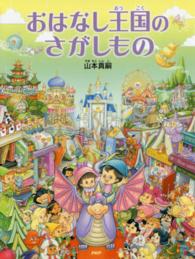出版社内容情報
アダム・スミスが創始した古典派経済学の完成者リカードウ(一七七二―一八二三)の主著.彼は「経済学の原理」と「課税の原理」とを別箇の次元にあるものとし,課税論はあくまで「経済学の原理」の応用領域として理論を展開した.本文庫のテキストは一八一九年刊の第二版であるが,初版・三版との異同はすべて訳注他に明記されている.
内容説明
リカードウの主著。「経済学の原理」と「課税の原理」を別個の次元で捉え、課税論は前者の応用領域として理論を展開する。
目次
第1章 価値について
第2章 地代について
第3章鉱山地代について
第4章 自然価格と市場価格について
第5章 賃金について
第6章 利潤について
第7章外国貿易について
第8章 租税について
第9章 原生産物に対する租税
第10章 地代に対する租税
第11章 十分の一税
第12章 地租
第13章 金に対する租税
第14章 家屋税
第15章 利潤に対する租税