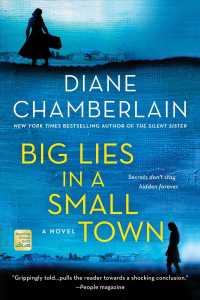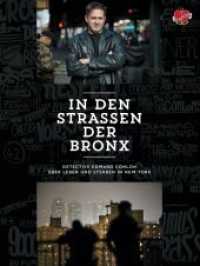内容説明
ダール(1915‐2014)は、理念としての「民主主義」と区別して、実際に存在する比較的民主化された体制を「ポリアーキー」と呼んだ。「参加」と「自由化」を指標とし、ポリアーキーの成立や変容を左右する政治的条件を分析する。現実を測り異なる政治体制に比較の道を開いた、民主主義理論史上画期をなす著作。
目次
民主化と公然たる反対
ポリアーキーには意味があるか
歴史的展開
社会経済秩序―集中か分散か
社会経済秩序―発達段階
平等と不平等
下位文化・分裂形態および統治効率
政治活動家の信念
外国支配
理論―要約と留保条件
補遺―変化の戦略のための示唆
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
逆丸カツハ
25
読みやすくて本質的で問題提起的で素朴に感動してしまった。SNSと生成AIの出現というかなり大きな条件の違いがあるが、アメリカが堕落していくかもしれない今読む価値はある。名著…!2025/04/12
1.3manen
18
1972年初出。民主主義の重要な特性は、市民の要求に対し、政府が公平に、責任をもって答えることだ(8頁)。ポリアーキーは、民主化・自由化された体制で、高度に包括的、公的異議申立てに広く開かれた体制(16頁)。重要な価値の配分の極端な不平等=政治資源の極端な不平等(131頁)。体制側は、疎外と離反で危険にさらされるので、国民によって憤激される極端な不平等状態は、体制側に脅威となる(143頁)。ポリアーキーは二方向の、相互のコミュニケーションを必要とする(228頁)。2014/12/16
ラウリスタ~
11
「民主主義」と言うと、「絶対正義!アテネ万歳!うせろ赤!」という具合にどうも手あかが付き過ぎて、正確にその実体を捉えることが難しい。ダールはx軸に包括性、y軸に異議申し立ての可能性を置き、原点を「閉鎖的抑圧体制」、上に行くと「競争的寡頭体制」、右へは「包括的抑圧体制」、そして右上の「ポリアーキー」へと広がる区分を提案する。このポリアーキーとはダールによる造語でまあ民主主義のことなんだけれども。各国が如何なるルートを辿って右上へと向かっているのかっていう比較もあり面白い。2014/11/21
那由田 忠
10
現在最も優秀な政治学者である宇野重規解説では、「20世紀政治思想の古典」と見なされるが、まだ有効性がかなりある。72年時点でポリアーキーが30年間にあまり増えないだろうとの予想が、冷戦終結のためかかなりはずれたと思う。しかし、「アラブの春」以降の推移を見ても、ダールの分析が広く知られていれば、民主化の成功がかなり難しいと考えられただろう。その意味で、この著作は今こそ重要とさえ言えそうだ。77年に訳者の高畠がダールと行った対談が付録でつく。訳者あとがきとあわせ、高畠がダールを理解していないのには笑った。2014/12/30
ドウ
7
言わずと知れた比較政治学の古典。参加の包括性と公的異議申し立ての2つの軸を用いて東西の政治体制をマッピングし、その両者が成立した体制を「ポリアーキー」と呼称し、様々な角度から分析を加えている。序盤に提示される主題の魅力もさることながら、だらだらと長文を重ねるのではなく、公理や定理を箇条書きにシンプルに並べてくれているのが、本書の圧倒的な読みやすさに繋がっている。第7章の議論が特に面白かった。2019/05/29
-
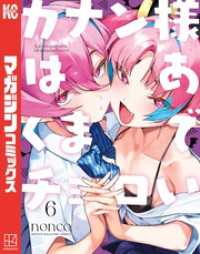
- 電子書籍
- カナン様はあくまでチョロい(6)