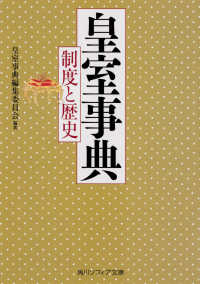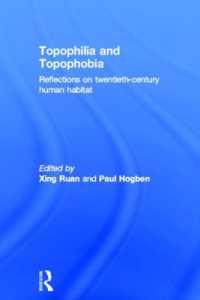出版社内容情報
19世紀フランスの政治思想家トクヴィル(1805―59)が,アメリカ社会全般の透徹した分析を通して広い視野で近代デモクラシーを論じた,現代の民主主義を考えるにあたって読み直すべき古典的名著.1835年に刊行された第1巻(第2巻は1840年刊)では,アメリカ社会の具体的な分析を行なう.(全4冊)
「すべてが新しい世界には新しい政治学が必要である」という意気込みをもってトクヴィルは本書を著した.その政治学は新しい世界を理解するための単なる客観的知識だけを意味しない.明らかに古い世界の中に生まれたトクヴィルにとって,新たな世界に自らの場所を見出し,その中で生きるために不可欠な認識をも意味した.その認識を彼は『アメリカのデモクラシー』を書くことによって獲得した.トクヴィルは本書を書いてトクヴィルになったのである.フローベールが「ボヴァリー夫人は私だ」と言ったのと同じ意味で,「『アメリカのデモクラシー』はトクヴィル自身の肖像である」と最新のフランスの研究は言う.
……トクヴィルはフランス人に向けてこの本を書き,「アメリカを描きながら,フランスを考えている」にもかかわらず,アメリカ人自身がこれをアメリカについての本として読み続けてきた長い歴史は無視できない.アメリカ人の自意識の中に本書は深く入り込んでいるのである.「アメリカについてこれまで書かれた最良の本」というアメリカの評者さえいる.
(「解説」より)
1 ~ 2件/全2件
-
- 洋書
- Random