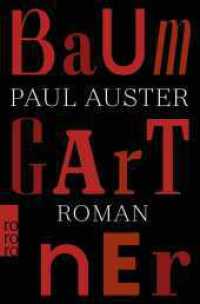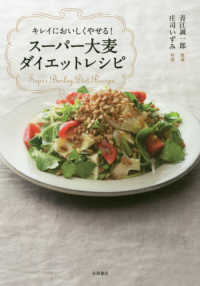内容説明
量子力学を創造し、原子物理学の基礎をつくった著者が追究した生命の本質―分子生物学の生みの親となった20世紀の名著。生物の現象ことに遺伝のしくみと染色体行動における物質の構造と法則を物理学と化学で説明し、生物におけるその意義を究明する。負のエントロピー論など今も熱い議論の渦中にある科学者の本懐を示す古典。
目次
第1章 この問題に対して古典物理学者はどう近づくか?
第2章 遺伝のしくみ
第3章 突然変異
第4章 量子力学によりはじめて明らかにされること
第5章 デルブリュックの模型の検討と吟味
第6章 秩序、無秩序、エントロピー
第7章 生命は物理学の法則に支配されているか?
エピローグ 決定論と自由意思について
1 ~ 3件/全3件