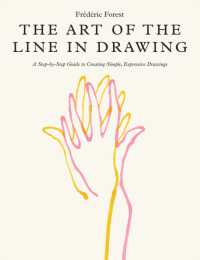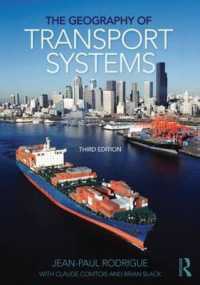出版社内容情報
社会学の創始者の一人にして、「生の哲学」を説いたゲオルク・ジンメル(Georg Simmel 1858-1918)は、宗教と宗教性を区別し、後者を人間のアプリオリな属性の一つとみなすことで、そこに脈動する生そのものを捉えようと試みた。社会学・心理学・哲学・美学の観点が交差し、ユニークな創見に満ちたジンメル宗教論の初集成。
内容説明
社会学の創始者の一人にして、「生の哲学」を説いたゲオルク・ジンメル(1858‐1918)は、宗教と宗教性を区別し、後者を人間のアプリオリな属性の一つとみなすことで、そこに脈動する生そのものを捉えようと試みた。社会学・心理学・哲学・美学の観点が交差し、創見に満ちたジンメル宗教論の初集成。社会と宗教の関係を考える上で示唆に富む一冊。
目次
1 社会学と認識論の視座(宗教社会学のために(一八九八)
宗教の認識論に寄せて(一九〇一))
2 生・救済・人格(汎神論について(一九〇二)
魂の救いについて(一九〇二) ほか)
3 芸術としての表れ(キリスト教と芸術(一九〇七)
レンブラントの宗教芸術(一九一四))
4 モダニティーとの相克(宗教の根本思想と近代科学 アンケート(一九〇九)
宗教的状況の問題(一九一一) ほか)
5 宗教/宗教性と社会(宗教(一九〇六/一九一二))
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ex libris 毒餃子
10
ジンメルの文章は難しい・・・。宗教社会学といえば、ヴェーバーだが論点・視点が違うということはわかった。2025/02/23
海
3
ジンメル本人の文体がすごく読みにくいのに加えて、日本語にすることの限界を感じさせる。読みにくいし場所によっては意味不明。芸術論とかは面白かったし、宗教において外面的な形式より内面が重要だ、というふうに読んだのですが、そういう考え方は賛成できる。2023/01/18
Go Extreme
2
社会学と認識論の視座: 宗教社会学のために 1898 宗教の認識論に寄せて 1901 生・救済・人格: 汎神論について 1902 魂の救いについて 1902 生の対立と宗教 1904 宗教哲学の一問題 1905 神の人格 1911 芸術としての表れ: キリスト教と芸術 1907 レンブラントの宗教芸術 1914 モダニティーとの相克: 宗教の根本思想と近代科学 アンケート 1909 宗教的状況の問題 1911 現代文化の葛藤(抄) 1918 宗教/宗教性と社会: 宗教 1906/19122022/01/24
フリウリ
1
なぜ人間は「人格神」をもつようになったか、の説明からが興味深い。人間は自らの欠点、不完全性を補填するために、神に人格を与えた。重要なのは、「「私たち」の生のことがら」である。だから、神が人の上に立つのではなく、人が神の下に立つことを考えよう。拡大された人間が神なのではなく、縮小された神が人間であることを考えよう。ジンメルは独特で、難しいけど、おもしろい。6/102022/09/04
R
0
社会における宗教の役割や意義を問うのが宗教社会学と考えているが、宗教と社会を分離して考えることが自明でなかった時代が長かったろうと思う。宗教=キリスト教を転換させたことも人類の学問の少しずつの発展を感じさせる。2022/09/17