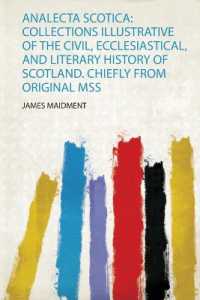出版社内容情報
「理性が世界を支配し,したがって世界の歴史も理性的に進行する」との確信にもとづき,世界精神の理性的かつ必然的なあゆみとしての世界史をヘーゲルは構想する.一八二二―三一年に五回にわたって行われた講義を彼の死後に編集・整理したのが本書である.「語られたことば」であることを配慮した明快な訳文でおくる.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェルナーの日記
80
近代哲学を2分化すると、前期近代哲学は、カントを代表する実存主義という思想が中心にあり、後期近代哲学は、カントの実存主義を継承・反証・展開などといった時代で、構造主義とか、ポスト構造主義といわれる。その中におけるヘーゲルは、カントの実存主義を継承しつつも、独自に展開し、人間中心主義(悪くいえば人間至上主義)を生み出した。このことによってサルトル(継承)やマルクス(展開)が存在し、反証としてレヴィ=ストロースが打ち立てたのが構造主義である。よって、近代哲学のヘーゲルが果たした役割は大きく、転換点を創造した。2015/01/25
i-miya
46
2013.03.16(つづき)ヘーゲル著。 2013.03.14 世界史において国家を形成した民族しか問題とならない。 国家こそが絶対の究極目的たう自由を実現した自主独立の存在であり、人間の持つ全ての価値と精神の現実性は、国家を通じてしか与えられない。 精神の現実性とは、人間の本質たる理性的なものを、対象として知ることであり、現実的なものが客観的な形ある存在として目の前にあることです。 国家の共同精神。 近年の国家論にある多くの誤謬いくつかに触れたい。 2013/03/16
i-miya
41
2013.09.07(つづき)ヘーゲル著。 2013.09.05 最善体制はどうか、という場合、私たちは主観の自由な信念に基づくかのように、そして、最善ないし次善の体制の導入が全く理論的な決断に基づいて行われ、体制は頭で考えればすむような、自然な選択によって決せられるものと考えがちである。 ヘロドトス『歴史』。 最初に国家を作るのは、強制的な、本能的な力です。 2013/09/07
i-miya
41
2013.06.16(つづき)ヘーゲル著。 2013.06.14 国家の在り方を考える。 その場合、第一に考えるべきことは、何か? それは支配者が、どこまでで、被支配者とどこで区別されるか、ということです。 その意味で国家体制がどうなっているかを考えねばなりません。 国家体制は一般に、(1)君主制、(2)寡頭制(貴族制)、(3)民主制、に分類します。 この分類は理にかなっています。 君主制は、さらに、(1)独裁君主制と、(2)本来の君主制に分けられます。 2013/06/16
i-miya
39
2013.05.28(つづき)ヘーゲル著。 2013.05.27 社会や国家はたしかに、制限を設ける。 しかし、制限されるのは、未開の鈍い感情や、粗野な衝動である。 加えて反省の加わった勝手な恣意や情熱です。 家父長制社会。 社会全体にとって、家長が支配する関係においてこそ、道徳的、心情的要素と正義の要素がともに満足が得られ、家父長制と結びついた正義こそが、その内容にふさわしい力を発揮する支配服従のつながりを含むもの。 2013/05/28
-

- 洋書
- Jurassic