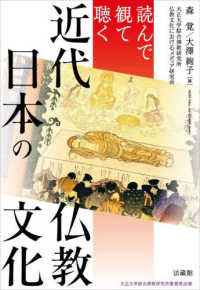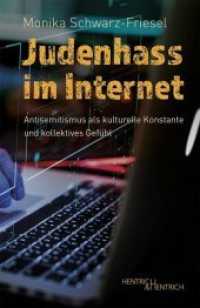内容説明
ルソーが言語の起源と本質を論じた著作。言語の本質とは情念の表現にあり、もとは言語と音楽の起源は同一であったという。言語の起源と変遷、諸言語の地理的差異、音楽の起源、旋律、和声の原理と歴史が分析され、南方と北方の言語の抑揚の相違、言語の現状が言語の変遷といかに関係しているかなどが論じられる。
目次
われわれの考えを伝えるためのさまざまな方法について
ことばの最初の発明は欲求に由来するのではなく、情念に由来するということ
最初の言語は比喩的なものだったにちがいないということ
最初の言語の特徴的性質、およびその言語がこうむったはずの変化について
文字表記について
ホメロスが文字を書けた可能性が高いかどうか
近代の韻律法について
諸言語の起源における一般的および地域的差異
南方の諸言語の形成
北方の諸言語の形成
この差異についての考察
音楽の起源
旋律について
和声について
われわれの最も強烈な感覚はしばしば精神的な印象によって作用するということ
色と音の間の誤った類似性
みずからの芸術にとって有害な音楽家たちの誤り
ギリシャ人たちの音楽体系はわれわれのものとは無関係であったこと
どのようにして音楽は退廃したか
言語と政体の関係
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イプシロン
28
言語と音楽の関係性についての本は幾冊か読んできた。だが、本書を読んで思ったのは、言語学知識の圧倒的な不足だった。しかし、本著自体は非常に楽しんで読めた。言語の起源は感情を伝えたいという心情の発露であり、そうして生まれた旋律が音楽の起源であるとするルソーだが、いささか強引で極端な思考が無いとは言いがたい。それでも言語の発展に気候風土が深く関わっている論理には首肯するしかなかった。個人的には旋律は感情を伝えるものとして優れ、和声は理性で捉えたものの意味性を伝える手段として発展したのではないかと思う。2021/12/11
ラウリスタ~
26
人々同士を遠ざける「必要、欲求」ではなく、人と近づきたいという「情念」が言葉を生んだ、だから原初の言葉は音楽的で韻文だった。言語の南北比較では、母音が快く響く快楽と雄弁の南方(ギリシャなど)に対して、子音で文節化された耳障りな北の言葉(フランス語含む)が対比される。イタリア語に対するフランス語の音楽的優劣が当時問題になっていてルソーはイタリア語派だったと。最後がかっけえ「集まった民衆に聞いてもらえないような言語は全て奴隷の言語である」。よく響き聞き取りやすい雄弁というのはそれほどまでに重要なのだと。2016/08/25
松本直哉
25
作曲家兼思想家らしく言語と音楽をパラレルにとらえ、言語の始まりは歌(旋律)だったと説く。言語が文法と文字をもつにつれて命を失い冷たい人工物になったと同様に、音楽も、和声をもったために自由を失ったと。機能和声の確立期にすでにその破綻を予告し、実際1世紀後のワーグナーを境にして、和声の時代は終る。エルネスト・アンセルメは「旋律はドミナントに向う弾道である」と述べたが、逆に言えばドミナントという着地点に縛られたために人間の歌は鳥の歌のような自由を失ったのだ。ワーグナーの無限旋律は和声から旋律を解放する試みだった2022/03/26
イプシロン
19
(再読)20世紀に飛躍的に発展した自然科学、論理学、そして言語学をあるていど知っているなら、本著でルソーが展開する論説の正否を問う読み方には、あまり意味がないだろう。ではどのように読めばいいかと問われるなら、こう答える。「彼の思考のしかたを学ぶために」あるいは「彼が何を理想とし、その実現に何が最重要であると考えたか」を読み取ることに意味がある、と。では、ルソーは一体になにを最重視したのか? と問われるならこう答える。哀れみの情(Pitier)である、と。したがって、彼の思考は常に「憐れみの情」を論拠の2024/10/21
吟遊
13
新訳で、ルソー研究史上ちょっとマイナーであった本書が登場。読みやすいが、ちょっと訳し分けがわかりにくい語もあった。だが、全体に注も多く、シンプルな訳文で、きっちりと解説もされているのはとてもよい。ルソーが独断で好き勝手言っている感じが楽しい。2018/03/15