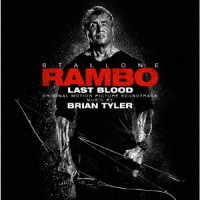出版社内容情報
ソクラテスは国家の名において処刑された.それを契機としてプラトンは,師が説きつづけた正義の徳の実現には人間の魂の在り方だけでなく,国家そのものを原理的に問わねばならぬと考えるに至る.この課題の追求の末に提示されるのが,本書の中心テーゼをなすあの哲人統治の思想に他ならなかった.プラトン対話篇中の最高峰.
内容説明
ソクラテスは国家の名において処刑された。それを契機としてプラトン(前427‐前347)は、師が説きつづけた正義の徳の実現には人間の魂の在り方だけではなく国家そのものを原理的に問わねばならぬと考えるに至る。この課題の追求の末に提示されるのが、本書の中心テーゼをなす哲人統治の思想に他ならなかった。プラトン対話篇中の最高峰。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のっち♬
145
個人の〈正義〉を国家の次元から考える代表作。〈不正〉の神々や他人からの感知は一旦傍に置く前提がとっつきやすく、イデア論・教育論・認識論と包括性が高い。原理的考察で建設される理想国家は欲望・感情・表現に節制を課す。文芸論になると口調が厳しくなる著者、詩に魅惑されつつテーゼと相容れないジレンマはかなり激しいらしい。家族・金銭の共有化など奇抜な発想や時代がかった価値観はあるが、事件や内乱は穏便に、貢献しない者は不要、戦争が不回避、支配者は哲学者であれ、などといった国家の本音は無駄を削いで構築したからこそ鋭利だ。2022/07/26
molysk
85
師ソクラテスを国家に処刑されたプラトンにとって、個人の正義を問うことは、国家の正義を問うことでもあった。国家においては、知恵ある守護者が勇気ある戦士を従えて、欲望に流されがちな大衆に節制をもたらすとして、守護者が戦士とともに大衆を従えることで正義が実現されるとする。個人の正義は、魂の理知的部分を守護者、気概的部分を戦士、欲望的部分を大衆に対比させて、理性が勇気とともに欲望を従えることで得られるという。そして、理想国家は知恵をもつ哲学者が守護者となって統治することで実現されるという「哲人統治」を説く。2024/01/13
esop
77
国家の在り方、ひいては国民一人ひとりはどうあるべきか、をソクラテスを通じて語らしめるプラトン。 長編の岩波だが、比較的読みやすい。 一つ一つの概念を対話形式で確認していき、革新に迫っていく。 真の哲学者とはーー真実を観ることを、愛するひとたちのことだ! 中心テーゼは哲人政治の有効性。2500年前に書かれたとは思えない。 キーとなる勇気、正義、知恵、節制とは何か?本書を読めばヒントが得られるかも!?2025/06/25
syaori
71
〈正義〉とは何か。それが「最高の〈善きもの〉に属すること」を示すため、「大きなもののなかにある〈正義〉のほうが」学びやすいという理屈から、「すぐれた国家の模範となるもの」を言葉で作成してゆく対話篇。この時代から、自己利益を追求する人間の本性に対し「法律をつくって契約を結んでいる」という社会契約説に繋がるような理論が出て来ることに驚きました。〈正義〉と〈不正〉について探求しながら「正しい国家」の条件や支配階級の資質を描き、その支配者である哲学者が目指す「真実」、恒常不変の善のイデアについて語り始めて次巻へ。2021/03/18
Gotoran
59
古代ギリシャ哲学者プラトンの中期対話篇全10巻、本書(上)は、5巻までを収録。ソクラテスとその他の知者たちとの問答で国家について問い質されていく。正義とは何か、という問答から始まり、理想の国家についての議論へと進んでいく。智恵、勇気、節制、正義が、理想の国家の四つの性質であると。全体主義、現代とはかなり感覚が異なる民主主義、ジェンダー論等々、近代や現代にも通じる思想テーマ、問題提起を垣間見ることができた。読みながら自己の考えを巡らせるという読書の1つの醍醐味を味わうことができた。 2019/04/07
-

- DVD
- アニキに恋して DVD-BOX1