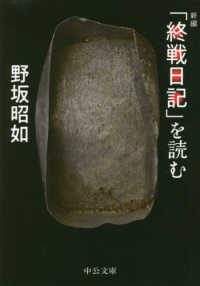出版社内容情報
一八七一年三月一八日、パリは蜂起した。蜂起からコミューン壊滅までの時々刻々の動きをドキュメンタリー風に再構成する。コミューンはパリ市議会選挙を行うも、さまざまな対立が時機を失わせ、次第に政府軍が巻き返していく。コミューンとは何であったのか。その意義を多角的に考察する。(解説=西川長夫)(全二冊完結)
内容説明
1871年3月18日、パリは蜂起した。蜂起からコミューン壊滅までの時々刻々の動きをドキュメンタリー風に再構成する。議会選挙を行い、コミューンを宣言するも、さまざまな対立が時機を失わせ、次第に政府軍が巻き返してパリは行き詰まる。コミューンとは何であったのか。その意義を多角的に考察する。
目次
第5部 三月一八日の事件(大砲事件―陰謀か、挑発か、力の見せしめか;三月一八日の夜と夜明け)
第6部 三月一八日からコミューンの宣言まで(自由の夜明け;中央委員会の仕事;反動派の再結集と政治の分裂;区長たちの陰謀;軍事情勢;地方の運動;選挙ろコミューンの宣言)
第7部 コミューンの生と死―結論(コミューンの暦;コミューンの重要性と意義;コミューンは成功しえたか;ティエール氏はなぜ勝ったか;事件についての一理論の草案)
付録(三月一八日の蜂起についての議会の調査;コミューンの祭り;パリにおけるインターナショナルの会議の議事録抜粋)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どらがあんこ
9
p356に引用されている「生まれながらに死刑宣告を受けたコミューン」という表現が印象的だった。中央委員会が陥った矛盾、権力のニ重性。また「自然発生性」による人民の全般的武装が組織的な軍隊に負けたのではなく、問題は習慣であったというところが面白い。「自然発生性」という一見偶然に見える要素もそれらと別のレベルで文脈によって規定されるものがあるのかなと。2018/11/11
古川
2
解説によると、本書は1968年のフランス五月革命とかなりリンクしているらしい。労働者階級が成長し自治を求め熱狂する都市部と発展から取り残されているがゆえに冷めた目で傍観する地方の農村部の対比や、労働者自治を粉砕するためなら平気で外国勢力と手を結ぶ反動政府など、21世紀の政治状況にも通ずるものがある気がする。むしろ現代においてよりよく読まれるべき本なのかもしれない。2017/07/05
1.3manen
1
原発再稼働反対デモ。その市民の結集が、日本でもようやく実行されてきた。これは、本著の内容ともつながる部分があると思える。ただ、武力衝突となると話は別だ。平和裏に終わることがこれからも続けばいいが、新政権ではこうしたデモもしにくくなると予見される。フランスも原発容認で、この史実をどうみるか。自由の夜明け(146ページ~)。社会科学の目的は自由の確保である。自由の伸びやかさ、清々しさ。中央委員会の宣言の一節で、「個人の尊重と個人の思想の不可侵」(275ページ)とある。個人の読書備忘録尊重の読書メーター、最高!2012/12/21
tamioar
0
よく分からない。2017/10/10
gauche
0
熱狂と狂乱のままにいつの間にか終わってしまった印象。2013/07/21
-

- 電子書籍
- 追放されたおっさん鍛冶師、なぜか伝説の…
-
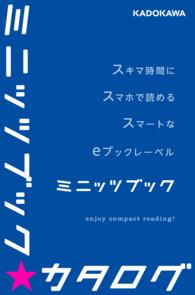
- 電子書籍
- カドカワ・ミニッツブック カタログ カ…