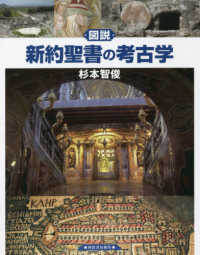出版社内容情報
明治も半ば,篠田鉱造(1871-1965)は幕末の古老の話の採集を思い立った.廃刀から丸腰,ちょんまげから散切,士族の商法,殿様の栄耀,お国入りの騒ぎ,辻斬りの有様,安政の大地震,道具の投売……幕末維新を目のあたりにした人々の話は,想像もつかない面白いことずくめだった.日本社会の激変期を語る貴重な証言集.(解説=尾崎秀樹)
内容説明
明治も半ば過ぎ、篠田鉱造(1871‐1965)は幕末の古老の話の採集を思い立つ。廃刀から丸腰、ちょん髷から散切、士族の商法、殿様の栄耀、お国入りの騒ぎ、辻斬りの有様、安政の大地震…幕末維新を目の当たりにした人々の話は、想像もつかない面白いことずくめだった。激変期の日本社会を庶民が語る実話集。
目次
幕末百話(江戸の佐竹の岡部さん;上野山門に屯集の賊徒ども;縁の下の力持(芝居の小道具)
水戸御用千住の鬼熊 ほか)
今戸の寮(錦絵のような生活;人力に曳殺さる;看板娘菊ちゃん;全盛期と没落期 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ねこ
116
明治35年夏、編者篠田胡蝶は報知新聞にて「夏の夜物語」「冬の夜物語」とし社説及び経済記事として掲載。紆余曲折あって、昭和4年に再販。当時の市井の古老に幕末期の話を丹念に聞き出し纏めるのは並大抵の苦労では無かっただろう。この岩波書は平成8年発行で現代風になっているがそれでもスラスラとは読みにくい。ただ、当時の古老の語り口が伝わり威風と粋を感じずにはいられない。切った張ったや殿様の浮世離れした私生活など生き証人の生の声には魅力があり幕末当時に引き込まれてしまいました。激動の時代だったんだなぁ。2023/12/02
esop
69
政治の要人ではなく、裏方である市井の人々の話を主題に、小噺100話が綴られる。 腹探りの話は面白い。 金時計を使って、みなの腹(考え)を巧みに引き出す。 当時も賄賂が横行して、話の種となっているあたりは、現代と何も変わらない。 人間ってノハァ愚かだナァ〜、厭世的になってしまう。 面白い話もあるが、半分以上斜め読みしてしまった〜2025/03/03
テツ
36
明治中頃に当時の老人たちに幕末から明治初期の話を聞いてまとめたもの。無名の、市井の人々が眺めてきた時代の移り変わりやそれにまつわる事件の数々。どのような歴史の転換期にだって普通に生きている人はいるし、普通の目線で社会を眺めているもんだ。歴史に名を残すような英雄ではなく、極々普通の人たちの目線で語られる昔のお話は面白かったです。2019/06/07
やいっち
28
幕末維新を古老に聞き書きしたもの。著名人は敢えて避けて、武士や商人、町民など多彩な人々の話題を豊富に。感想ならぬ気になる点は、これまで随時、メモってきたので、裏話の数々を楽しんだとだけ書いておく。2018/11/26
tsu55
25
市井の人々が語る幕末・維新史。昔の人の口調をそのまま記録しており、落語のようで面白い。付録の「今戸の寮」は別荘地であった隅田川河畔の風景が目に浮かぶようで、楽しめた。2016/09/27
-
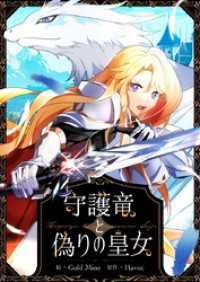
- 電子書籍
- 守護竜と偽りの皇女【タテヨミ】第6話 …
-
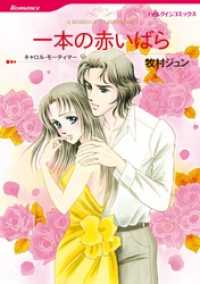
- 電子書籍
- 一本の赤いばら【分冊】 2巻 ハーレク…