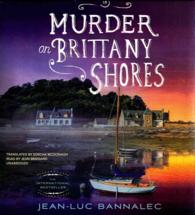出版社内容情報
明治大正期を代表する木彫家で,西郷隆盛銅像の製作者として知られる高村光雲(一八五二―一九三四)の自伝的回想録.「お話し自身すでに立派な芸術」といわれるほど座談の名手であった光雲が,息子の高村光太郎,田村松魚を相手に,生い立ちから彫刻家として名をなすまでを幕末維新の世相風俗を交えながら生きいきと語る. (解説 酒井忠康)
内容説明
明治大正期を代表する木彫家で、西郷隆盛銅像の製作者として知られる高村光雲(1852‐1934)の自伝的回想録。「お話し自身すでに立派な芸術」といわれるほど座談の名手であった光雲が、田村松魚や息子の高村光太郎を聞き手に、生立ちから彫刻家として名をなすまでを幕末維新の世相風俗を交えて生きいきと語る。
目次
私の父祖のはなし
私の子供の時のはなし
安床の「安さん」の事
私の父の訓誡
その頃の床屋と湯屋のはなし
高村東雲の生い立ち
彫刻修業のはなし
「木寄せ」その他のはなし
甲子年の大黒のはなし
仏師の店のはなし(職人気質)〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヨーイチ
33
大昔、姉の購読してた雑誌の付録で著名な音楽家と画家を集めたカードがあった。表に肖像と名前、裏に業績が書いてあり、クイズ形式で芸術家を覚えられるって趣向だった。母と姉に遊んで貰っている内に芸術家の名前だけは矢鱈と詳しい子供が出来上がっていた。高村光雲の名前は禿げと白髭のイラストと共にこれで覚えた。当時、大人の常識としては「光太郎」の父ってのもあったはず。西郷像と楠公像を手掛けた、最高峰の仏師にして彫刻家。面白かったのは江戸以来の仏師という職とその周辺。2017/08/09
tsu55
13
口述筆記なのだそうだが、高村高雲はよっぽど話し上手なのだろう、江戸から明治にかけての職人の暮らしぶりが生き生きと描かれていて楽しめた。2018/06/02
壱萬参仟縁
7
現代の自分史。彫刻修行(34ページ~)。評者は小学校卒業作品の木彫の鑿を入れたのを想起した。いい塩梅で彫り加減が重要なのである(43ページ)。象牙でなければ彫刻でない(181ページ)。そんな時代もあったようだが、現代では印鑑だが、象の殺し過ぎの問題も心配だ。生物多様性に影響するからである。浮き彫りにされた像をみると、人生が滲み出る人物像も写真にある。何を浮き彫りにするのか。それは、彫る人の人生をも反映する筈。自分史もその彫刻のような陰影が投影されるのは自然だと思った。人間も木の年輪のように、皺も貫禄あり。2012/12/28
駄目男
5
光雲という人は華美なことの嫌いな地味なタイプなのか世の時流に逆らって廃りつつあった木彫に飽く迄も拘り、師の教えを生涯忠実に守った彫刻師だったように捉えたが、年季の明けた明治七年頃は多くの仏師が廃業を余儀なくされ、翌八年には神仏混淆の廃止、廃仏毀釈の嵐が吹き荒れる時代に突入。しかし光雲の信念は変わらず、幕末、明治、大正、昭和と生き八十二歳で没した。この間、世の変転凄まじく世相の移り変わりなど時間をかけて訊きたいものである。後年、光太郎は光雲のことをいろいろ書いているが、親子の確執とは何だったのか知りたい 2017/10/13
ともゑ
3
明治時代に活躍した彫刻家、高村光雲氏がこれまでの半生を振り返って語る本。話が上手くて引き込まれる。面白い。これは高村氏自身の半生の話でもあるんだけど時代はちょうど幕末から明治維新。当時の世相を語る貴重な資料の1つかも。2013/07/15