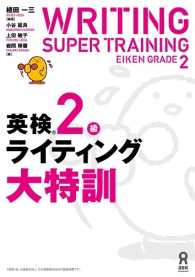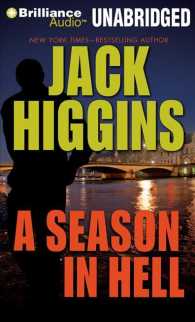出版社内容情報
明治十年六月,来日間もないモース(一八三八―一九二五)は露出した貝殻層を東京に向かう汽車の窓から目撃し,それが先史時代の遺跡であることを看破した.日本考古学の第一歩というべき大森貝塚の発見である.その発掘報告書『大森貝塚』は,観察と実験に徹する科学精神をみごとに体現し,今もなおわれわれを圧倒してやまぬ.
内容説明
明治10年6月、来日間もないモース(1838‐1925)は東京に向う汽車の窓から露出した貝殻層を目撃し、それが先史時代の遺跡であることをただちに看破した。日本考古学の第一歩というべき大森貝塚の発見である。その発掘報告書『大森貝塚』は、観察と実験に徹する科学精神をみごとに体現したものであって、今にわれわれを圧倒する。
目次
大森貝塚の一般的特徴
大森貝塚の特徴
土器
装身具
土版
角器・骨器
石器
動物遺体
食人の風習
扁平な脛骨
大昔および現生の大森軟体動物相の比較
図版解説
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
52
読んでたようで、読んでなかった。特徴。第一に、莫大な量の石器。形態さまざま。無限の変化をもつ装飾。第二に、石器類が極度に乏しく、石鏃・石槍の尖頭器がないという(25頁)。 シュリーマン『古代への情熱』も読みたくなった。長野県立歴史館、近く行ってきたい。2022/03/02
misui
6
日本考古学の原点ということでなかば野次馬気分で。時代が時代なので今では考えられないような記述もありつつ、発掘資料を網羅的に載せるというようなところは素直に凄い。凄いが、後に続く人がいなかったとのことで、ために日本の考古学は50年は遅れたらしい。あと当時の学術誌上での感情丸出しのやり取りとか。モースの活躍が生まれたばかりの進化論に支えられていたことは特に覚えておこう。ダーウィン本人も出てくる。2017/09/27
space shatoru
3
原点を読んだという感じですね。今では、大森貝塚の位置づけとして、研究者の多くは読むべき一冊となっています。ただ、位置づけとしては学史として一冊という評価になってきているかもしれない。けれども、学史の本質を知る上でも、考古学徒は必読の書ですね。2014/11/13
塩崎ツトム
2
日本考古学が幕を開ける瞬間を切り取った記録の書。貝塚から先史時代の一端を垣間見るだけでなく、「はたして日本に食人の習慣があったのか?」「アイヌ民族が本州島から去ったのはいつか?」という幅広い議論が海の向こうで繰り広げられていたというのも興味深い。2013/07/24
はるゆう
1
人食について、いろんな人が、ああでもない、こうでもない、といろいろやり取りしているされていて、面白かった。ところで、江戸時代以前の人たちは、貝塚には興味がなかったのだろうか。どういう認識だったのか、ちょっと興味が出てきた。 それと、外国人に、日本の文化物の海外流出を心配されているとは・・・。日本人が日本の持っているものの価値をきちんと認識できないってのは、昔も今も変わってないような気がする。2012/01/21