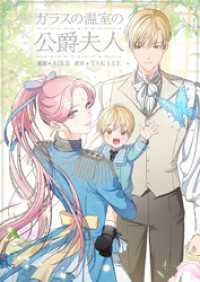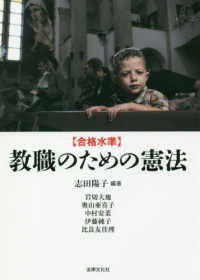出版社内容情報
平安末期から鎌倉時代にかけて,法然,栄西,道元,日蓮,親鸞,一遍ら,新仏教の旗手たちが踵を接して登場した.天皇・公家から一般の庶民まで,多くの人々に帰依された,浄土宗の開祖法然(1133-1212)の伝記.(全2冊)
内容説明
平安末期から鎌倉時代にかけて、栄西、道元、日蓮、親鸞、一遍ら、新仏教の旗手たちが踵を接して登場した。その先駆けとなったのが、浄土宗の開祖法然である。他力念仏により極楽浄土に往生することを説き、当時の天皇・公家から一般の庶民まで、多くの人々に帰依された法然の伝記『法然上人行状絵図』(知恩院蔵)。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
ワタシのおしごと用本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
13
浄土宗開祖の法然上人の伝記。であるのだが本人が出てくるのはごく一部で、ほとんどは浄土の教えとその勧め、妙好人の伝記で成り立っている。ただそれも全て法然の語りかけという形式で説かれているため、浄土教の要点が非常にわかりやすくなっている。あと絵伝というわりには、絵自体はあまり載せられていなかった。2012/03/27
1.3manen
6
脚注を頼りに読む以外ない本。「愚童持斎心」とは、人間らしい心をおこし、自己を反省し、日常生活をつつしもうとする心(39ページ)。これは豪奢を避ける心がけとしたい教訓だ。説法会の様子(54-55ページ)。現代は葬式や法事以外、あるか否か。否だろう。懺悔は死ぬ間際にしても手遅れだと思った。普段から、死ぬ間際との認識をもっているなら、懺悔をする回数は増えるが、それだけ謙虚に生きることができ、おてんとうさまも見ているだろうから(天知る、地知る、吾知る、汝知るの如く)、心がけておければ死ぬ直前に後悔することはない。2012/12/20
はるたろうQQ
2
法然上人の異能な所は目の隅から光が出て暗い所でも経が読めたことではなく、己を煩悩具足の凡夫と規定し、そんな人間でも救われる道を懸命に模索し、阿弥陀仏の本願による救済と専修念仏を発見したことにある。富貴の者から下賤の者まで救いを求めその門に入ったのは自らに真摯に向き合うと人間は輪廻の里を出離できないことが明らかだからだ。人間に妄執があることを前提に念仏をまず唱えることを説くのも印象的だし、女人往生を明確に述べたことも特筆すべきことだ。世の常なる尼女房たちが歓喜の涙を流してみな入門したとの記述は感慨が深い。 2020/06/03