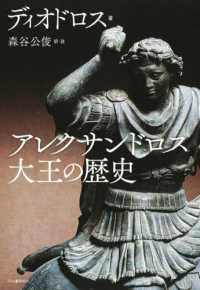内容説明
大拙の事実上のデビュー作Outlines of Mahayana Buddhism、1907、の邦訳。明治新仏教の到達点の一つであり、二十世紀のZen Buddhismの起点ともなった書。過去の仏教の解説でなく、現代に生きる新たな宗教としての「大乗仏教」を思想と実践の両面から提起する。智慧と慈悲の統一を説く理知的にして情熱的なその筆致は、今もなお生命を失わない。
目次
序論
思索的大乗仏教(実践と思索;知識の分類;真如(bhutatathata)
如来蔵とアーラヤ識
無我説
業)
実践的仏教(法身;三身説(仏教の三位一体説)
菩薩
菩薩道の十段階―我々の精神生活の階梯
涅槃)
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
姉勤
29
禅の大家と知られる著者が、明治期渡米した際、欧米に溢れる仏教の誤解を解こうと、英文で著した本書を邦訳。主にキリスト教徒へ向けたもののため聖書を引用、比較することが多い。ただ皮肉なことに、訳者や解説の通り、著者の誤解や誤認、独自の解釈が少なくなく、大乗仏教の概論というよりは、日本教、ひいては「大拙経」というべきもので、著者当人が、再販や翻訳を禁じたというのも無理もないが、個人的にはこれもありなんじゃないかと思うほど、愛(悲)の発露なくて、どうして他人様を導けようか。2023/01/04
テツ
18
鈴木大拙による大乗仏教の概要。どんな事柄でも語る人間の主観により大なり小なり本来のコトやモノからのズレは生じてしまうので、あくまでも鈴木大拙の宗教観だと踏まえた上で読まなければならない。大乗の修行の目的は自分独りで悟りに到達し解脱することではない。その末に人々を救うために、それが叶う人間となるために身も心も全てを捧げ全身全霊で修行をする。一切衆生を救うという望み自体が煩悩に塗れたエゴではあるのだけれど、それでもそうした強い狂気にも似た想いには強さと美しさが輝いて見える。2022/01/11
OjohmbonX
13
400ページにわたる大乗仏教に関する西欧の誤解の批判とコア認識の解説を読み終えたと思ったら、訳者後記で「この本は誤謬だらけで、事実誤認と都合の良い取捨選択で成立しており大乗仏教の解説ではない」と全否定されていて、でも「これが真の仏教」みたいな顔で自説を展開するのが経典だから「大拙大乗経」だと思えば偉大、って擁護が入ってほっとしてたら、続く解説で「実はこの本は別の人の本のパクリです」って指摘が紹介されて自説の展開ですらない、えっ、じゃあ俺が読んでたのはいったい何だったんだ、と途方に暮れる、すごい体験だった。2016/10/23
roughfractus02
7
1907年英文で書かれた最初期の著作である本書は、ベルギーの仏教学者プサンに、日本仏教からの大乗解釈であり、内容もヴェーダーンタ的なヒンドゥー哲学寄りであると指摘され、その後著者がヒンドゥー的思想面から日本仏教的実践面に重心移動する書物を書く契機となったとされる。一方本書は、歴史上の小乗との対立を取り外し、多様な解釈を引き起こす仏陀の教えを含めた経典作者達の「神秘的感情」の伝達過程として大乗仏教を捉え直す点にある。その伝達過程に参入する著者は、大乗に衆生に潜在する「菩薩心」覚醒の実践というテーマを見出す。2021/02/27
モリータ
7
37歳の鈴木大拙が英語で海外出版したものの和訳。岩波だし簡潔・客観的な入門書にいいだろう、と思って手にとった。が、訳者(佐々木閑氏)あとがきを読むと、学説上の誤り(根本経典の年代が下ることなど)や主観的教理解釈が多分に含まれており、現代の入門書としては読めない(一種危険な本である)ことがわかる。当時の西洋の仏教理解に対して著者が打ち出した「大拙教」として味わうとか、オーソドックスな大乗仏教との対比や後期密教やヒンドゥー教の影響を考えるとか、ちょっと高度な楽しみ方ができればと思いますが、私にはまだムリです。2018/03/22
-
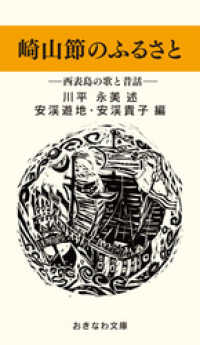
- 電子書籍
- 崎山節のふるさと―西表島の歌と昔話― …
-
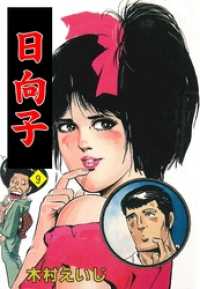
- 電子書籍
- 日向子9巻 マンガの金字塔