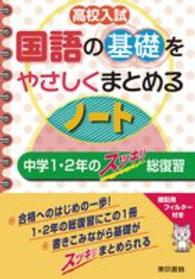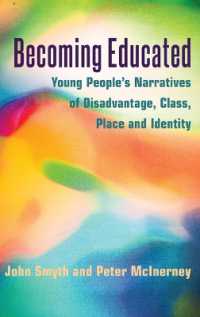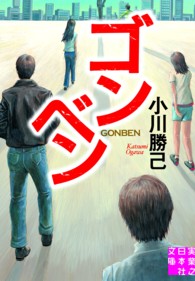出版社内容情報
中国文学史の研究に巨歩をしるす著者(一八八七―一九六四)が精深な知識と体験をかたむけてものしたエッセー十二篇.大陸で多彩な発達をとげた各種粉食の歴史,江南の地でついに賞味するを得た紹興酒の絶品の話,筍を焼いて食う話など,食いしん坊と上戸にはこたえられぬ佳篇ぞろい,しかも学問の太い筋が通っている. (解説 戸川芳郎)
内容説明
中国文学史の研究に巨歩をしるす著者が、その精深な知識と体験をかたむけてものしたエッセー12篇。中国大陸で多彩な発達をとげた各種粉食の歴史、江南の地でついに賞味するを得た紹興酒の絶品の話、喫茶法の変遷、筍を焼いて食う話など、食いしんぼうと上戸にはこたえられぬ佳篇ぞろい、しかも学問の太い筋がびしっと通っている。
目次
粉食小史
愛餅の説
愛餅余話
饂飩の歴史
落雁と白雪〓
用匙喫飯考
花彫
末茶源流
焼筍
〓菜譜
付録(陶然亭;花甲寿菜単)
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
24
米の糗は粒食に適し、麦の糗は粉食に適する。故に糗を粉食することは、麦の糗の使用から起ったのではないか(29頁)。薄餅(パオピン)とは金糸玉子を造る時の薄焼きのような具合に円く、極めて薄く焼いた餅(43頁)。蝦油というのは、蝦の塩辛が腐爛して溶解した汁(167頁)。安全か? 白菜で珍妙なのは北京の酸菜(スワンツァイ)で酸味帯びるも、京都の酸茎のように塩漬が発酵して自然に酸っぱくなったもの(170頁)。食文化のつながりとして、木曾のすんきは京都のとは味が違う。 2015/10/16
どらがあんこ
10
ただ美味だからというだけでなく、名からその食物を考証する筆者はまさに文化を「享受」しているのだなと。膨大なテクストの引用に加えて著者の体験の記述によって、見たこともない異国の食べ物への食欲を掻き立てられる。決して夜中に読むものではない。あと附録『陶然亭』は酒徒の皆さん必見かと。2018/11/03
Ex libris 毒餃子
6
『随園食単』から引き続き、中華料理の本を読む。中国文学の知識をフル活用して、中華料理の解説をしている。当方仙台民につき、妙に仙台をディスってるのは気になった。2019/06/24
isao_key
5
中国の食についての随筆。いわゆる皇帝料理の類の話ではなく、一般の庶民が普段食べている料理について述べる。団子の話に始まり、うどん、落雁、匙と箸、はたまた酒、茶、筍、漬物など縦横無尽に筆を進めている。この本の優れた点は、単にあの時、あの店で食べた一品は実に美味かったと回顧談を述べているのではなく、ひとつひとつ文献にあたり、時代考証をしているところにある。その薀蓄がまた微に入り細を穿っている。例えば『混沌』という熟語は餅が一定の形を成していないことから来ているなど。明治の知識人の教養の高さにまたも恐れ入った。2012/10/18
松本左都夫
3
僕は甘党(ついでにおし○こまで甘い(*_*))で下戸ですが、「陶然亭」と「花甲寿菜単」は、もうもう…牛?やがな…もう、素晴らしいの一語。アマポチ(Amazonでポチッとな)が出来て、ばんざーいヽ(´ー`)ノです。