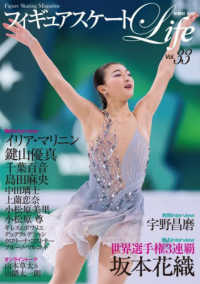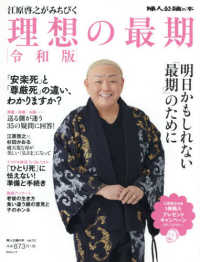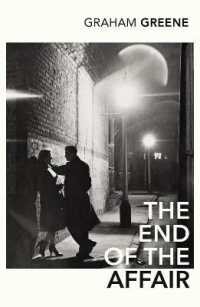出版社内容情報
著者の故郷である山口県大島の明治末から大正にかけての暮しの中に,子どもの躾のありようを描いた出色の生活誌.『忘れられた日本人』をはじめ多くの優れた業績を遺した宮本民俗学の原点を示す書であり,子ども・民俗・教育を考える人への格好の贈り物.故郷の風土を克明に描いた「私のふるさと」を併収. (解説 原ひろ子)
1 ~ 1件/全1件
- 評価
稲岡慶郎の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
50
周防大島の明治大正の民俗記であると同時に、宮本家家譜、著者の幼少期の自伝でもある。共同体が壊れる以前の子供の躾や近所付き合い、村でのそれぞれの役割等教えられる事が多いが、それ以上に胸に迫るのが幼少期の思い出を描いた部分。特に著者の父親が旅立つ息子に贈る餞の言葉などは言葉に書かれている以上の含蓄を含み、世代を超えて親の共通した気持ちではなかろうか。同時収録されている「私のふるさと」は同じく幼少期の思い出が詩情溢れる文体で綴られており、今はもう戻らない風景を書き出したものとしてこちらの方も心に迫る物が多い。2014/04/03
chanvesa
32
冒頭に「われわれの胸をうつ今次の戦の軍神を草莽の中に」(14頁)などという言葉が出てくるのが戦時中らしい。しかし女性は銃後の守りのような価値観ではなく、生き生きとした人間像が描かれる。女性は子供のために生き、子供を守るといった姿勢が現代において、端的に通ずるかというのは一概に言えないかもしれないが、美しい生き方の一つのように思える。一方で若い女性達のいたずら「ぜんざいの中に唐辛子」(164頁)も微笑ましい。戦争より前の日本の人々の生活の基準に「孤独を感じない」(193頁)ことに重きを得ていたことは重要。2017/09/21
いの
29
「西瀬戸内海」筆者の故郷。その場所で子供の時にみたこと教えられたこと経験したことそして考えたことを記録している本です。形が変化してもなお残っていること滅びて記憶のなかで活きているものを豊かに記していました。私達日本人の歴史の一部分を垣間見ながら我が故郷の山と生活を思い出し懐かしさと感謝の気持ちで満たされました。集落全体が家族であり子供の幸を願い発展に望をかける大人の姿が写し出されています。文中より「…自らの酬いられるところの少ないのを不満としない風の多いのは将来というものを信じ得るからであろう」。2020/04/14
tsu55
16
民俗学者宮本常一が、生まれ育った故郷である山口県周防大島 の暮らしぶりを描いた生活 誌。 行ったこともない土地の、しかも僕が生まれる前の時代の記録なのに、何故か読んでいて懐かしい気持ちになった。2025/07/14
浅香山三郎
14
『忘れられた日本人』が言はば列島のあちこちを歩くことによる、非近代的な日本人の生き方のかたちの記録だつたとすれば、本書は著者の故郷・周防大島の人びとや、著者の生まれた村、親族らが話したり、行動したりしたことからなる生活誌が丹念に綴られる。生活と生産と土地が深く結びついたかつての生活世界の広がりがよく分かる。昭和18(1943)年の、著者の大阪府鳳町在住時代の著作である。2021/12/06