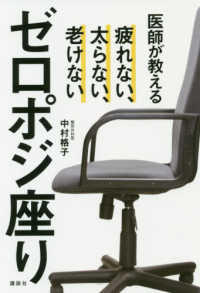出版社内容情報
医を志して江戸に出,維新に際会して一時中断するが再開,山県有朋らの知遇を得て陸軍軍医制度の創立・確立に尽力した石黒の自伝.「近代医学事始」ともいうべき苦労話,徴兵制度・兵食問題など,近代日本の一側面が内側から語られ興味つきない.俊秀な軍医としての森鴎外も活写されている.「祖父忠悳のこと」(原もと子)を付す.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ジャズクラ本
18
○司馬による岩波文庫私の三冊の最後の一冊。著者は松本良順を師とする江戸の蘭方医で、日清日露では軍医制度を確立。日本赤十字の設立に寄与。看護婦制度導入も。司馬の「胡蝶の夢」がその多くの事歴をこの本から拾っていることがよくわかる。一方、明治軍医制度樹立の頃の松本良順が傲岸であったとか、吉原の妓楼から診療に通っていたといったことは胡蝶の夢には(僕の記憶では)書かれておらず、司馬小説にはない側面を知ることができて興味深かった。同郷の井上円了が石黒の学塾の教え子だったことも初識。勉学意欲の旺盛さは随一だったようだ。2020/02/07
壱萬参仟縁
7
第一期で、「私も貴君(大島氏)と同行してまた木曾路から信州へ帰りましょう、と相談を決めました」(77頁)と地元の地名が出てきた。京都を発って8日目に塩尻駅に着きました(78頁)ともある。佐久間象山先生は、顔色白いが、髭が黒く長い。目は大きい。炯々(光り輝く、広辞苑)人を射る眼付(99頁)。風采は文化人らしさを感じる。二宮尊徳先生の場合を想起するような、柳家にいて写本や読書するにも、燈火に油が要る。普通の種油では高価なので、魚油を使ったという(131頁)。今、円安で灯油もガソリンも高い。読書会も遠方は辛い。2014/01/22
穀雨
5
陸軍省医務局長や日清戦争の軍医方トップなどを歴任した人物の自伝。明治初年に生活上の必要から町医者の書生となってわずか数年で、日本の保健衛生行政を取り仕切るまでに出世したのだから、明治初期はきわめて流動性の高い、風雲の時代だったことが伺えた。佐久間象山との出会いなど、若かりしころの幕末の話もいろいろ興味深い。2021/10/16
午睡
5
幕末に生まれ、明治に陸軍衛生部で軍医制度を確立した石黒忠直( 直は略字。正しくは直の下に心と書く)の自伝。森林太郎などの上司にあたる。後ろ盾もないまま一念発起して学問とラジカリズムに打ち込む少年時代から筆が起こされるが、この時代のラジカリズムとはもちろん尊王攘夷で、佐久間象山との面会にこぎつけ、象山が書いた長い碑文を本人の前で誦じてみせ驚かせる回想など、じつに読ませる。 功なり名をあげた人だが、若き日に出会い別れた友を終生忘れなかった。歴史の中に緘黙して消えていったその友、大島誠夫の姿は鮮烈な印象を残す。2020/07/25
にゃん吉
4
勤皇の志士から西洋医学を志し、陸軍軍医となり、行政官として軍事上の医療、衛生に辣腕を振るい、軍医総監に昇進し、医務局長を務めたほか、貴族院議員や日本赤十字社社長も務めた、石黒忠悳の自伝。このような経歴が語られる中で、幕末、明治期の西洋医学の受容過程、明治政府における行政組織の有り様、近代的新制度が整備される過程の一端等が知られ、また、佐久間象山、山県有朋、大山巌、後藤新平等々の交流や面識のあった人々の一面が知れます。日清戦争が語られる件は、医療、衛生の観点から見た戦記という趣があります。 2023/08/18