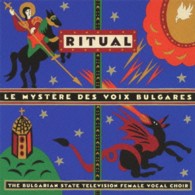内容説明
国の独立は目的なり。今の我が文明はこの目的に達するの術なり―西洋心酔と保守主義の相確執する明治初期、文明の本質を論じ、文明は文明自らに意味があるとした上で、今、最も優先すべき課題は日本国の独立であり、西洋文明を学ぶのもそのためであると説く。『学問のすゝめ』と共に、時代の展開に大きな影響を与えた福沢(1835‐1901)の代表的著作。
目次
第1章 議論の本位を定る事
第2章 西洋の文明を目的とする事
第3章 文明の本旨を論ず
第4章 一国人民の智徳を論ず
第5章 前論の続
第6章 智徳の弁
第7章 智徳の行わるべき時代と場所とを論ず
第8章 西洋文明の由来
第9章 日本文明の由来
第10章 自国の独立を論ず
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
40
権力の偏重への懐疑を述べたもの。田舎の百姓は正直なれども頑愚なり、都会の市民は怜悧なれども軽薄なり(19頁)。一長一短。文明とは英語にてシウヰリゼイションと云ふ。羅甸語のシウヰタスより来りしもの。文明とは人間交際の次第に改りて良き方に赴く有様を形容したる語にて、一国の体裁を成す(51頁)。人生の目的は衣食のみに非ず。若し衣食のみを以て目的とせば、蟻の如き、蜜蜂の如き。心を高尚にするのみを以て文明と云はんが(54頁)。 2016/07/04
長谷川透
22
明治初期に書かれた著書とは思えぬ福沢の達観に何度も度肝抜かされた。支那、朝鮮、日本という直線的な関係、そして西洋列強の支配に怯える強者対弱者の関係を瓦解させ、近代化に突き進もうとする日本という新国を、世界という舞台に内包し、グローバリズムの中で捉え直そうとする試みにまず舌を巻いた。デリダ以前の西洋が半開と卑下していたこの国で脱構築的な知性を展開した偉人がいたのだ。地理的歴史的な分析も去ることながら、判断の下し方が独善的ではなく、判断を下すには長い歴史の洗練を受ける必要があると説く懐の広さにも好感が持てた。2013/01/14
masabi
16
福沢諭吉の最高傑作にして現代でも通ずることの多い内容を含む。漢文調で読むのに手こずったのと理解できていない点が多々あるので現代語訳されたものも読んでみたい。国の独立を目的に、文明を手段と置く。先んじて文明化していた西欧列強を手本としながらも無批判に受容せず、批判すべき点は攻するという、西洋書物や知己との知的格闘を経た彼独自の思想ともなっている。2016/01/20
しゃん
15
明治初頭の日本が置かれた情勢を踏まえ、日本がこれから進むべき道を指し示す名著。ある時は舌鋒鋭く、ある時はシニカルに。本書の論述はリズムがいいので、福澤先生の巧みな演説を聞いてるような錯覚に囚われるときがある(二重否定の文が多いのは苦労したが。)。中長期的視野に立ちつつも、喫緊に対処しなければならない事項を優先順位を付けて示していく思考法は学ぶところが多い。それにしても、福澤先生の和漢洋の該博な知識には圧倒される。そして、それらの知識を咀嚼して料理していく様は圧巻。福澤先生は、今で言うグローバル人材だな。2017/03/20
まふ
12
文明の何たるかを手際よく論旨明解に述べている。日本人の歴史がいかに人民の成長を無視した形で行われ、半開の国であるかが納得的に説明されている。学問のすすめほどリズム感はないが、全体に名文で綴られている。福沢はまこと文章の達人であったことがよく分かる。譬えの文が豊富かつ具体的である。今日においても全く古さを感じさせない古典と言うべきであろう。2001/10/21
-

- 電子書籍
- 絶世の悪女は魔王子さまに寵愛される 分…