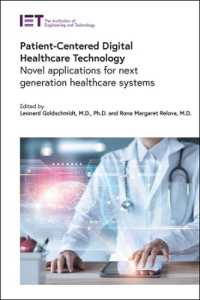出版社内容情報
福沢諭吉は友人とともに繰り返し『蘭学事始』を読んだが,『ターヘル・アナトミア』の原書を前にした玄白たちが「艫舵なき船の大海に乗り出だせしが如く」ただただ呆然とするばかりだったとある条に至るや,常に感涙し無言に終ったという.蘭学創始にあずかった先人たちの苦闘の記録は今も鮮烈な感動をよぶ.
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ベイス
95
「老齢作品でこれほど人を感動させた書物はほかにあるまい」と山田風太郎が評したが、期待以上の名著だ。学を成すとは?60ページほどの短い文章のそこかしこに、かけがえのない言葉が敷き詰められている。杉田玄白が83歳で著した、『解体新書』誕生の回想記。洋学の先進性に触れた江戸中期の学者たちの驚き、無知だった己への叱咤と激励、利他主義ともいえる探求心、困難に立ち向かう強い意志と謙虚な心。判読不能な蘭学書を前にして「艪舵なき船で大海に乗り出すが如く」。福沢諭吉が毎度ここで落涙するのも大げさではあるまい。2023/10/12
esop
80
スマホやネットがない世界で、全くわからない言語を前にし「誠に艪舵なき船の大海に乗り出だせしが如く、茫洋として寄るべきかたなく、ただあきれて居たるまでなり」とつぶやいている。 こんな状況の中で翻訳を終えた時の感動は一入だったのだろう。 福沢諭吉は繰り返し読み、感涙したという。 先人達の日本を進めようと言う意志が今日の医療発展、国の発展につながっていると思うと、胸が熱くなる。 読みづらいが、なんとなく、なんとなくだけど、雰囲気は感じ取ることができた。2025/03/06
ヴェネツィア
63
本書は上之巻、下之巻の2巻で構成されるが、面白いのは断然上之巻。下之巻は後日談及び、その後の蘭学者列伝といった趣き。明和8(1771)年3月4日に千住骨ヶ原で「腑分」(人体解剖)が行われ、玄白や良沢等がこれを見学。持参した『ターヘルアナトミア』の図と全く同じであることに驚嘆。翌日から翻訳にかかるが、「わずか一二寸ばかりの文章、一行も解し得ることならぬ」状態から、ついに3年半後『解体新書』を上梓するまでの苦難をその43年後に、に83歳の玄白が回想する。途中には平賀源内のエピソードなどもあり、大いに楽しめる。2013/04/08
藤月はな(灯れ松明の火)
26
卒論の参考資料として読了。遠近法と陰影法による写実主義を日本画に取り入れた秋田蘭画の創始者、小野田直武が『解体新書』の挿画に関わっていたということ、直武に絵画技法を教えた平賀源内が蘭画を蒐集していたことについての確認として。「対象を実際に見て客観的に写実する」ことを主にした写実主義。実際に解剖に立ち会うことで『ターヘル・アナトミア』の正しさを知る玄白。だが阿蘭陀語を日本語に訳すのは難しかった。客観的に事実を見た上で誤りなく、訳すことへの忍耐強さやそれを愉しむことのできる心意気も教えてくれる。2014/12/12
yamomerkは本を読む
17
最近購入、一日で爆読読了。…素晴らしい。ドラマティック!福沢諭吉が繰り返し読んでは涙したという有名部分も含め、全て読めて幸せだった。(昔教科書で読んだところの、「フルヘッヘンド=堆し」という鼻の定義語が解体新書自体に記載なし、などという新発見も巻末の解説で知ることが出来た。)玄白先生は常に「生民救済」を目指していた。先生を産んですぐに亡くなった母君、先生に内臓を晒して『ターフェルアナトミア』の翻訳を決意させるきっかけとした刑死者の青茶婆、あなた方「生民」も蘭学→近代日本への橋渡しの一員だったかも…合掌。2020/05/31