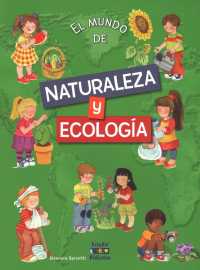出版社内容情報
西川如見は宋学を修め,天文暦算に長じ,また先儒の諸説やヨーロッパの説を参酌して発見する所多かった江戸時代の学者.その著書20冊余のうちから撰んだこの3書は,それぞれ町人道徳,農民経済,長崎古事等を,その博識を駆使して通俗に談話風に書かれた処世修養の書.江戸時代の道徳を知る上に見逃すことができない名著である.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
9
「商のみちとは、金銀をもつて物を買とり、利倍をかけてうれる事をのみいふにあらず。商の字の心は、商量といひて、物の多少好惡をつもりはかりて用をなし利得を得るは、みな是商の類なり」(15頁)。つまり、商人は善悪の判断がつかなければと。CSRの原点である。悪利では困る。「富て驕ることなきは易しといへども又かたし。況や富て礼を好む人をや」(31頁)。「心つよく、むごき心なくては財寶を多く貯(たくはゆ)る事あたはず」(32頁)。「我船の順風は人の舟の逆風」(33頁)。この認識がないと、格差社会を越える発想はでない。2014/01/17
猫丸
2
表向きは封建道徳の奨励だが、天文、暦学者としての西川如見の科学的精神が漏れ出ている部分が面白い。神仏を尊崇する一方で啓蒙精神も見られる例として、金銀に富む島から貴金属を載せて去ろうとする船が当該の島から航行できなくなる故事を、土地の神の罰との解釈を排し、磁鉄鉱が船内の金属を引きつけるのでは、と考察するなど。近代精神の萌芽を見る。2018/07/04
天婦羅★三杯酢
0
鎖国中の江戸時代、それでも唯一外界との接触を公式に認められた長崎で上級商人であった西川如見の遺した書。内容は、基本的には江戸初期の幕府公認の儒教的道徳訓である。それが、昭和16~17年に岩波文庫として出版され(そして18年に重版出来)た意味というものを考えてみたい気はする。2016/04/24
-

- 電子書籍
- 恋する2DK、あやかし前妻憑き。【分冊…
-

- 和書
- 俺様の宝石さ