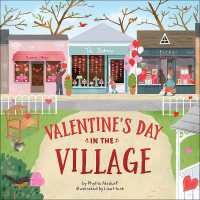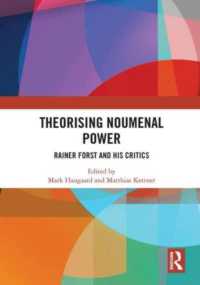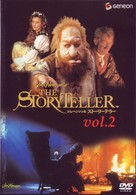内容説明
イタリアの寒村に育った私生児のぼくは、人生の紆余曲折を経て、故郷の丘へ帰ってきた―。戦争の惨禍、ファシズムとレジスタンス、死んでいった人々、生き残った貧しい者たち。そこに繰り広げられる惨劇と痛ましくも美しい現実を描く、パヴェーゼの最高傑作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
332
親もわからない孤児であった「ぼく」は、やがてジェノヴァを経てアメリカに渡り、そこで経済的な成功を果たして村に帰郷する。「成長物語」との見方もあるが、これは「ぼく」が何かを得る物語ではない。むしろ、ここに語られるのは喪失の物語であり、漂泊する魂の物語である。「ぼく」が故郷を離れていた間に多くの人が亡くなったが、最も象徴的なのは小説の最期に語られるカンティーナの物語だろう。「ぼく」は、故郷は、そしてイタリアはなんと多くのものを失ってしまったのだろう。戦争は終わったが、パヴェーゼの絶望は深い。2016/06/09
ケイ
147
美しく静かな故郷への郷愁。貧しさと戦争が村の人々を奪っていった跡。金持ちのあさましさ、貧しい農民の無知からくる無謀、もたらされる悲劇。なのに、村は変わらず、自然は美しい。住んでいた人の死も悲劇も、静かに抱きこむ。その村の出身ではないから、どこが生まれかを知らず故郷も持たないから、親と思っていた人達に去られた自分だから、村の美しさに抱く郷愁はとても強い。しかし、アメリカで財をなしたとて、それがなんになる?そこに留まり様々な事を見届けているヌートの地に足の着いた強さは、主人公の過分な感傷をあやふやにする。2016/09/08
まふ
117
「月と篝火」のみを読む。第二次世界大戦時のイタリア農村における村の有力者一族が運命に翻弄される顛末を中心に描かれた作品。「私生児」である語り手は地元の資産家の下男、志願兵、脱走兵となりアメリカに労働者として渡り故郷に戻る。資産家の長女イレーネ、次女シルヴィア、三女サンティーノの夫々が不幸な境遇と終焉を迎える。物語は三女の死をもって終わるが、そこまでに至る紆余曲折は読み手の心に重い感慨を齎す。この作家は初読であり暗い作品であったが行き届いた正確な叙述が印象に残った。G530/1000。2024/06/07
扉のこちら側
108
2016年375冊め。【186/G1000】夏至の夜に豊穣と再生を願って焚かれる篝火。それは死者を供犠する炎でもあり、私はこの祭りに、雰囲気がまったく違うはずの日本のお盆を思い出さずにはいられなかった。「うなぎ」が憧れていた美しい三姉妹もそれぞれ悲劇的な死を迎えたことが明かされる。「去年までそこに残っていた、篝火を焚いたような跡が」。少年チントは炎から逃れ、「うなぎ」の再来となっていくのだろうか。その炎は、新たな時代の始まりを照らす篝火か。2016/06/06
どんぐり
92
アルバにある大聖堂の石段の上に置き捨てられた私生児。貧農の一家に引き取られ、兵役を機会に村を出てその後アメリカに渡り、みなが忘れたころに財を成して帰ってきた「ぼく」という主人公が語る物語。彼を迎えたのは、人が孤独でないことを告げる故郷とサルトの丘の大工のヌート、そしてかつての「ぼく」を見るかのようなチントという少年。「村人たちのなかに、植物のなかに、大地のなかに、おまえの何かが存在し、おまえがいないときにもそれが待ちつづけていた」故郷は、ファシズムとレジスタンスの戦禍が押し寄せ、村人を巻き込み血に染めてい2016/06/10
-

- 和書
- 法医看護学
-
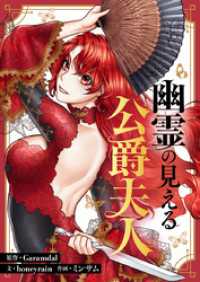
- 電子書籍
- 幽霊の見える公爵夫人【タテヨミ】第13…