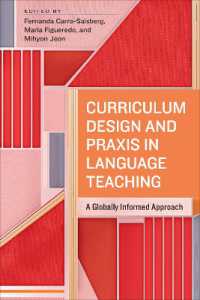内容説明
二〇世紀の演劇を革新した演出家・俳優の自伝。劇作家ダンチェンコと運命的な邂逅を果たし、新しい劇団を構想するスタニスラフスキー。二人の創設したモスクワ芸術座は、大家トルストイ、新進のチェーホフらの作品で、旧弊を破る革命的な舞台を実現する。疾走する青年時代。
目次
俳優の青年時代(続)(演出家的課題への熱中―『ポーランド系ユダヤ人』;本物の役者たちとの経験;『オセロ』;トリノの城;『沈鐘』;意義深い邂逅;モスクワ芸術座の発足を前にして;最初の演劇シーズンの開始;劇団公演の歴史的・風俗的路線 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ラウリスタ~
4
スタニスラフスキーさん、僕はあんたについていきます。 と、言いたくなる。数少ない人生の師となるだろう人。この人は本物だ。この人は自分の専門分野である演劇のことしか語らない。それでいてすべてを語っているのだ。自分が知らないすべての事柄について語り、それでいて何事も語らない人々と比べるとその差は歴然。 ロシアって決して豊かな歴史を持つわけでもないのに、なぜこれほどまでの芸術を生み出したのか。ソ連の存在がつくづく恨めしい。あいつがいなければ今の世界はもっと素敵になっただろうに。詳しくはブログで2011/02/18
MILK
1
スタニラフスキーがダンチェンコと出会い、劇団が形になっていくあたりです。やはりひとつのシステムを作り上げるほどの人だけにスタニラフスキーの人物の観察眼は鋭くてとても興味深い。中盤以降のチェーホフの描写は特に楽しく読みました。2009/10/05
1.3manen
0
チェーホフ『桜の園』に注目した。「病人が、自分自身によって死を宣告された者が(略)、近親や友人たちから遠くはなれ、自分の前に一条の光を見ることなく、彼の憎悪する場所に、囚人のようにつながれた者が、それでもなお、未来の世代のための文化的な富を貯えることに気をくばりつつ、笑うことも、明るい夢想と未来への信頼に生きることもできるとするならば、―そのような生の喜びと生命力は、異常な(略)ものと認めねばならない」(305-6ページ)。病と闘う者への驚きと懐疑が相混ざったようなとらえかたをしているようだ。2012/08/05