出版社内容情報
17世紀フランス文芸の中心をなしたオテル・ド・ランブイエに出入し,のち寡婦となってからルイ14世の宮廷に出,ラ・ロシュフコー,ラファイエット夫人等ひろく当代の名士文人と交遊を続けた作者(1626‐1696)の書簡集.娘の結婚を中心とする5年間の手紙を集めた本書には当代のあらゆる人びとの肖像が窺われ,その文体は古典的香りが高い.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
syaori
49
17世紀、ルイ14世の時代を生きたセヴィニエ夫人の有名な書簡集のうち、主に娘の結婚、出産に関する手紙をまとめたもの。上品に、時に洒脱に綴られる、夫の任地へ旅立った娘への手紙に溢れる愛情ももちろんですが、宮廷から遠く離れた娘に伝えるニュースもこの書簡の魅力ではないでしょうか。大姫様(モンパシエ夫人)の結婚や王の愛人ラ・ヴァリエールの二度目の出奔、また料理人ヴァテルの死の経緯について書かれた部分は、生々しく当時の宮廷の人々の視線を伝えるよう。そのほか、流行の髪形についてなど女性らしい話題にも興味津々でした。2018/01/04
おMP夫人
8
朗読・吉永小百合。そんな想像を勝手にしてしまい、原文でも読んでみたいと思う上品で薫り高い文章でした。内容はフランス貴族のご婦人が嫁いだ娘さんにせっせと送り続けた書簡集なのですが、これが溺愛を感じる内容で微笑ましく、娘からしてみれば「わかったわかったお母ちゃん、もうええから」と言いたくなるほどの筆まめぶり。そんな風に思ったのは、私が母親ではなく娘の立場だからなのかもしれません。親の心、子知らずとはよくいったものです。期せずして母の日を間近に控えた時にこの本を読めたのはとてもよいめぐり合わせでした。2013/05/10
きゅー
6
遠く離れた場所で暮らす娘への手紙が主として収められている。自分の娘にもはや二度と会うこともできないかもしれないという哀しみと愛情と共に、身近な話題やフランス宮廷のゴシップが綴られる。ラファイエット夫人、ラシーヌ、ラ・ロシュフーコー、コルネール等錚々たる顔ぶれの名前が、お茶会のメンバーのひとりとして挙げられるとは、なんと贅沢なことか。遠く離れた人との連絡手段は手紙のみの時代の心細さといったら想像もつかない。愛する娘の声を聞くことも出来ず、その文面から様子を推し量ろうとする親心の寂しさよ。2012/03/11
iwag
2
結婚しはじめて離れて暮らすことになった娘グリニャン夫人に宛てた手紙。パリの風俗とか身辺の話が主なのだが、その中に離別の悲しみ再会を望む激しい思いがよく表されてるし、持てる才知をすべて注ぎ込んだのだろうと伺える。「お手紙をもらうとまた次のが欲しくなります。お手紙をもらうより他に念頭はないのです」「そういった人たちを求め、他の人たちを遠ざけてきました」もあるよ。他の手紙も読みたいけど日本語訳ってこれしかないんだよな…。2011/12/11
ぜっとん
1
『失われた時を求めて』からの流れで読んだが、これは寝る前に少しずつ読むのにいい。井上究一郎さんの、几帳面だが茶目っけある文体も好きだ。2014/12/14
-
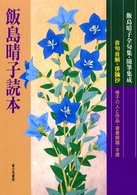
- 和書
- 飯島晴子読本








