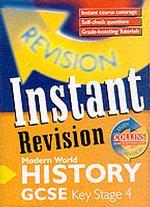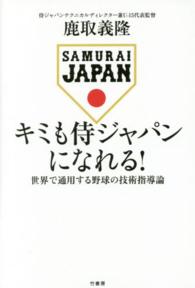出版社内容情報
「光こそ万人のもの」という思想の下に展開された国際的平和運動の契機となった作品.「戦争はいやだ」と叫ぶ民衆の声が,奴隷の精神を捨てて搾取階級の打倒へ向わねば平和を守ることはできない,という主張を作者はこの小説で明らかにする.ロシア革命の翌年に書かれ,レーニンは前作「砲火」と本書とを激賞した.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
みっぴー
35
『クラルテ』とは〝光〟や〝光明〟を意味するフランス語です。第一次世界大戦に従事した主人公を通して反戦を謳った作品ですが、主人公の一人言を聞いているようで、はっきり言って退屈でした。話題も戦争から家庭生活、労働へとあっちこっち飛び、結局何が言いたいのか…と。要はドイツ軍国主義を打倒し、戦争を操る指導者や貴族を抹殺して労働者による社会を実現しようということが主張らしいです。後に『クラルテ運動』という反戦運動にまで発展した本書ですが、きっと発表当時は衝撃だったのでしょう。2016/07/11
壱萬参仟縁
27
嫉妬は社会の癌で、 公民の偉大な美徳、 規律の敵(119頁~)。 格差があれば余計に。 道徳は個人の欲望の束を 他人のそれにしたがって 調整する。 道徳は、使命の自然の結果 として、同時に全体と 個人から、理性と利己心 から生ずる。 理想こそすべて道徳から出た (249頁~)。 正義といい権利というのは、生命。 あらんかぎりの生命。 人間であり、あらゆる時代の 人間(333頁)。 真実のなかには平等があり、 現実のなかには不平等がある。 人間悪のはじまりは人類の はじまりにみとめられる(347頁)。 2014/06/12
讃壽鐵朗
3
不思議な魅力で読み通してしまった。 第一次大戦に今興味があるのも一因だが、訳文が本当に熟れていてまるで日本人作家の作品であるかのように読めたのだろう。 読了後、つくづく、これほどひどい戦争をやったのに、同じ欧州でその後20年にしてまた第二次大戦を起こしたことが信じられない。 人間は、所詮は未だに闘争心を持った動物であることを再認識させられた。2014/12/06
KUMAGAI NAOCO
2
けっこう難解な本。アンリ・バルビュスの砲火と並んで読まれる本。主人公(シモン)は中流階級の何不自由ない生活をしてる男だが、第一次世界大戦に従軍し、戦地で負傷して生死を彷徨った事がきっかけで、世界平和と社会主義的というか、コスモポリタニズムに目覚めていくという話。独白体で真理について考える章とかもあり、哲学書みたいだった。2022/01/27
ペンギン捜査官
0
バルビュスは...本当に戦争にうんざりしていたんだろう。資本主義の台頭から第一次世界大戦の勃発、西部戦線を経験した彼にとって、庶民の平穏を何よりも望み、世界主義の可能性を唱え、社会共産主義を支持するに至ったのは自然な流れのように思える。 「砲火」でも聴かれた彼の叫び!本書の主人公ポーランもバルビュスだ。十六章以降で彼はポーランの身を借り、その冷静で鋭い怒りを吐露した。戦火に翳った、、塹壕に遮られた「光」を、彼は人民に見出した! この書はバルビュスという人間の精神・思想の到達点を、十全に解読できるだろう。2025/03/03