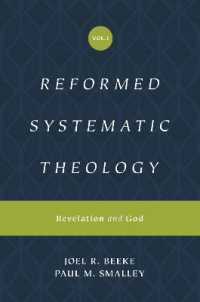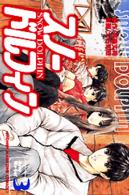出版社内容情報
文学,そして芸術への限りないあこがれを持つ一方で,世間と打ち解けている人びとへの羨望を断ち切ることができないトニオ.作者マンの若き日の自画像であり,ほろ苦い味わいをたたえた「青春の書」.(解説=濱川祥枝)
内容説明
「最も多く愛する者は、常に敗者であり、常に悩まねばならぬ」―文学、そして芸術への限りないあこがれを抱く一方で、世間と打ち解けている人びとへの羨望を断ち切ることができないトニオ。この作品はマン(1875‐1955)の若き日の自画像であり、ほろ苦い味わいを湛えた“青春の書”である。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のっち♬
131
「最も多く愛する者は、常に敗者であり、常に悩まねばならない」と芸術家に憧れる一方で俗世に憧れる少年。28歳の若さで描く10代は生への愛情が直截明瞭。人生と芸術家の関係の追求と共に、敬愛する先達へ際限なき憧憬を身近に感じた時代の空気や感覚を残したかったのかもしれない。反復や対句の効いた律動的な文体、象徴性を駆使した耽美的な表現、著者の優しく温かな眼差しを丁寧に汲んだ翻訳も素晴らしい。"凡庸なものに対する俗人愛"を訴える結末に後年のヒューマニズムな芸術観の予言が見られる。芸術と敵対する資本主義へ立ち向かう礎。2023/05/17
ナマアタタカイカタタタキキ
78
著者自身が文学者としてどうあるべきか思い悩んでいたことが窺える自伝的作品。『月と六ペンス』を彷彿させるテーマだ。芸術家としての感性と一般市民としての感性の狭間で葛藤する様は、たとえ芸術家を志していなくとも、多くの読者にはどこか覚えがあるであろう普遍的なものではないだろうか。“横道に逸れた俗人”は、決して稀有な存在ではない。元々人間は、理性の世界と感覚の世界の両方に属しうる中間的な存在だ。あまりにセンシティブな魂は、遠く離れた対岸から眺めると、ただただ愚鈍なだけに見えてしまうことがある。逆も然り、→2022/01/08
kasim
37
『魔の山』に比べると初期の作品で長さも10分の1以下だが、似た雰囲気が漂う。一般社会と芸術を二項対立で捉えるのはいかにも20世紀初頭。とはいえ面喰いゆえに美形に惹かれ、しかし対象の内面が自分と同質ではないことを見て取り、時には失望し時には自分の方を否定する、というのは多くの人に覚えのある青春だろうと思う。自意識ぐるぐるモダニズム。帰郷して知人もなく、博物館になった生家をよそ者として訪れるのは切ない。でも30歳で「人生を無駄にした」と悔いに苛まれるというのは早いぞ。2023/05/23
syota
36
①作者の「青春の書」とのこと。これほど理屈っぽい青春の書も珍しい。「踏み迷っている俗人ね」というリザベタのことばがトニオを端的に表しているが、この場合の「俗人」は原文ではBürgerで、ハンザ同盟などの中核を担った有力な市民を指す言葉らしい。日本語の「俗人」とはニュアンスが違うので要注意だ。奔放な母の血をひき詩人として退廃的な生活を送りながらも、まさにBürgerであった父譲りの堅実で禁欲的な価値観を捨てきれず、芸術家の世界にも一般人の世界にも居場所を見つけられない悩みを綴っている、と私は受け止めた(続)2018/10/30
長谷川透
35
皆とは違った眼差しで世界を見ている。芸術を志す若者が見つめる世界は、それを志す者らしく才能の片鱗も随所で見せてくれる。しかし、彼の目を通して書きだされる世界は、ガラスの如く脆い。特異でありたい願いと共にある、己を理解して貰いたい気持ち。凡庸に世界を見つめ、その世界の中で生きる人々をどこかで蔑みながらも、物事との距離を上手く掴み上手く世間を渡る人々を羨ましくも思う。トニオ・クレエゲルの抱える二つの願いは二律背反とは思わないし、折り合いをつけることが不可能なものであるとは思わない、が、若さ故の悩みなのだろう。2013/12/09