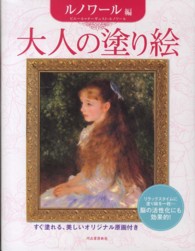出版社内容情報
激動の時代を熱烈に生きて戦った詩人ハイネ(一七九七―一八五六).祖国ドイツでの彼の評価はめまぐるしく変わり,ナチス支配の時代には完全に抹殺されさえしたが,その秀麗な抒情と卓抜な批判精神は,国境を越え時代を越えて数多くの読者を持った.一八二七年刊の『歌の本』は,青春時代の抒情詩の集大成で,シューマンらの作曲で愛唱されている.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
18
「おもえば くらい」で。 「おもえば くらい生活にでも やさしいひとの光は射した いまではそんな光も消えて すっかり闇につつまれている」 (9頁)。 今の日本は、ちょっと前からの 閉塞感。震災復興ヴォランティア。 それも放射能やスタグフレーションで 徐々に退潮気味か。 「人間よ」で、 短いものは人生だ、 と、 長いものは人生だ、 と対になっているのは 人生の特徴をよく言い当てている (59頁)。 2014/06/05
双海(ふたみ)
8
ハイネさん、下巻です。「夢にいとしいひとを・・・」(65頁)がとりわけ気に入りました。本文庫に挿入されているエッチングもまたいいですね。ハイネさんの友人ラウベが編纂した『ハイネ作品集』から採ったそうです。ハイネ記念版に協力した19世紀後半のウィーンの画家たちの筆になるものです。2014/02/23
tieckP(ティークP)
6
ここまで読み通してみて分かったのは、この詩集は「教養詩集(ビルディングスゲディヒテ)」とでも呼ぶべきものだということである。ナイーブだった序盤の詩から、物語詩、民謡風の抒情挿曲を経ることによって、神話・伝説や民謡の抽象的次元で詩を詠むことを学ぶ。後半ではそうした距離感に自信をつけたからこそ、一度目の失恋相手の妹への二度目の失恋という題材に果敢に挑み、個人と神話的物語との重ね合わせに成功する。シュレーゲル兄から学ぶことでロマン派から出発したハイネは、これにて後まで師と仰ぐヘーゲルの止揚を身につけるのである。2021/09/29
しんすけ
6
ハイネの詩(うた)の特徴は、垣間見える軽妙な知性でなのでないだろうか。それはある時は痛烈な諧謔とも読み取れる。ぼくはそんなハイネが大好きなのだ。だから、『歌の本』でも後半の物語的な長詩は好むところではなかった。 だが久しぶりに『歌の本』を手にし、後半の部分にもハイネの知性が輝いているのを識った。詩集というものは小説と違い、繰り返し読むことで味わいが深まるものかも知れない。2017/12/16
ダイキ
4
「はるかなる地平線/まぼろしの絵のごとく/塔のある町うかぶ/夕闇にたゆたいて/しめりたる風ながれ/灰いろの水跡(みあと)ひき/かなしげに橈(かい)をこぐ/わが舟の水夫(かこ)あわれ/陽はまた地平より/あらわれて輝きつ/わがために かのひとと/わかれたる地を照らし」〈はるかなる……〉2016/08/22
-
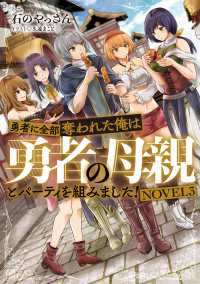
- 電子書籍
- 勇者に全部奪われた俺は勇者の母親とパー…
-

- 電子書籍
- noicomi 眠れるケモノは愛を叫ぶ…