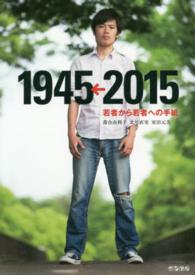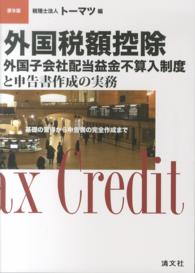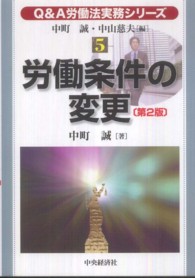出版社内容情報
ケルト民族のホメロスといわれ,またオシァン風という言葉が残ったようにゲーテその他のヨーロッパ文学に大きな影響を与えた本書も,わが国では漱石が一部手を染めたほかは正確に紹介されることがなかった.現身のはかなさも大いなる自然の変転の一部とみて響き美しくうたい上げてゆくケルト民族の心のうたをゲール語原典から初めて訳出.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
105
すばらしい文章で情景が浮かんでくるような感じです。日本語訳でもこのようなすばらしい散文詩が鑑賞できるのですね。私は純粋の文学として楽しみました。いわゆる後世にできたものだとか議論はあるのでしょうが、そのようなことに惑わされないで読みました。またかえってケルトの知識があまりないので人名や地名を気にしないで読みました。2017/08/21
syaori
44
年老いたオシァンが息子オスカルの許嫁モルヴィーナに語るのは今は亡き者たちの物語。彼は何と見事に歌うのか、父フィンガル王や勇士たちの勲を、彼らを慕う白い手の娘たちの哀切を。同時にそれは何と無常と孤独を感じさせるのか。父王も、共に戦った兄弟や勇士たち、息子さえも今はなく、彼らの戦捷や高い胸の乙女とのロマンスは、ただ一人、仲間を忘れられない老オシァンのなかにしか存在しないのだから。しかし彼のその歌が時を越えて届く時、哀しく美しいその歌はどれほど胸を震わせるものであったことか! 「歌人よ、歌声を高く高く上げよ」。2017/09/20
壱萬参仟縁
22
ニーベルンゲンの歌? 勇ましい感じがする。あとがきによると、雄大な荒涼とした自然を背景に壮大な人間の劇が展開(450頁)。古体と新体の混在(470頁)。詩の形式でもなく、かといって、小説でもないので、各まとまりをどう読んだらいいのか、苦労する。まとまり単位で捉えるだけでよいものか、と。一文の終わりの「。」が付いていないので。戯曲的な箇所もあるので、余計に読解のポイントがわからない。「タイモーラ 第八の歌」で、「自分の手は弱い者を危害から守り、傲慢な者は自分の怒りの下に消え去った」(403頁)が気になった。2014/03/03
ホームズ
15
騎士物語といわれるとどうしてもアーサー王と円卓の騎士のイメージが強くどうしても比較してしまうけど、やはりだいぶ違いますね。古い時代の物語ということでやはり荒々しい感じがする。名前が結構ややこしいというか似ているというかかなり覚えにくくてかなり読むのに苦労してしまった。2012/06/08
サアベドラ
6
勇壮にして美しく、悲しいスコットランド・ハイランド地方の英雄叙事詩。18世紀に世に出て以来、アイルランドやイングランドの歴史家から偽書扱いされ大論争を引き起こしてきたいわくつきの書でもある。現在は現地の古写本や口伝をもとに訳者マクファソンが大幅に加筆、再編成したものとされている。韻文の翻訳であること、回想が頻繁に挟まること、固有名詞が似ていることなどからかなり読みづらいが、物語と情景描写の美しさ、せつなさはただただ凄いの一言。2010/03/30
-

- 和書
- 万葉集論攷 〈1〉