出版社内容情報
インド文化の初頭を飾りインド哲学の本源をなす重要文献.すべて口授で伝承され,後にサンスクリット語で集録された.もろもろの神を讃えて,財産,戦勝,長寿,幸運を乞い,その恩恵と加護を祈った歌が,悠久三千年を経た今日なお人の心に迫るのは,古代人のおおらかな精神と人間らしい生活がよく映し出されているからであろう.
内容説明
インド最古の宗教文献であるヴェーダのうち、紀元前13世紀を中心として永い間に成ったリグ・ヴェーダはとりわけ古く、かつ重要な位置にある。それは財産・戦勝・長寿・幸運を乞うて神々の恩恵と加護を祈った讃歌の集録であって、アーリア人がのこしたこの偉大な文化遺産は、インドの思想・文化の根元的理解に欠かすことができない。
目次
ウシャス(暁紅の女神)の歌
ラートリー(夜の女神)の歌
スーリア(太陽神)の歌
サヴィトリの歌
プーシャンの歌
ヴィシュヌの歌
パルジャニア(雨神)の歌
ヴァーユまたはヴァータ(風神)の歌
ヴァーユの歌
ヴァータの歌〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
27
繁栄のために牽獣はあれ。 繁栄のために人々はあれ。 繁栄のために鋤は耕せ。 繁栄のために革紐は[軛(くびき)に] 結ばれよ。 繁栄のために突棒を振りかざせ (209頁)。 繁栄のために人間がある。 衰退のためにはない。 しかし、日本は没落中である。 [みづから]食物に富みながら、 食餌を求欲(ぐよく)しつつ・零落 して近づき来たる貧困者に、―― [しかも]かつて友好を結びし者に―― 心つれなく振舞う人、かかる者も また憐愍者を見いださず(349頁)。 貧困者に愛、思いやりを! 2014/06/13
姉勤
22
紀元前1500年前の、神々や自然への讃歌から下世話なモノ(浮気防止から賭博の詩)まで。素朴で欲張りな詩で溢れる。異民族を当然の様に駆逐する表現が多いのも先進の戦車(車輪)と農法,詩を編める文化を有し、インド亜大陸を支配したアーリア人なら当然なんだろう。その力の象徴のインドラ(雷神),アグニ(火神)などの神々は今日のインドでは強い信仰を喪い、傍神の暴風神ルドラ(シヴァ)が出世し、最高神となっているのが面白い。バラモンは既に高い地位を有しているが、インド思想特有の輪廻,カルマ,チャクラなどの表現はまだ現れず。2013/09/10
roughfractus02
9
全1028篇から174篇を抄訳した本書は、紀元前2000年頃からインドに侵入していたアーリア人の習俗が韻律豊かな詩形式で口承され、紀元前1200年頃に文字にまとめられたという。天・空・地・水で構成される多自然信仰が作る多神教宇宙は、火(アグニ)、雷と戦い(インドラ)、風(ヴァーユ)、神聖な飲み物(ソーマ)等儀式に必須の神々が重視され、神と繋がる貴重な機会として祭祀があったこともわかる。また、個々に意志を持つ神々は宇宙を統一的規則でなく複雑性として示す。性愛から宇宙に至る本書の語句には呪力も含まれるという。2026/01/05
isao_key
7
リグ・ヴェーダは、サンスクリットの古形にあたるヴェーダ語でかかれ、多くの神々をたたえ、財産、戦勝、長寿、幸運を乞い、その恩恵と加護を祈った讃歌の集録。優秀な讃歌と甘美な供物、特に神酒ソーマを捧げる祭祀とで、神々を満足させ、庇護者の願望を達成し、自己の競争者を凌駕して多量の報酬を得ることが、当時の詩人兼祭官の関心事であったという。ソーマの効験で、ソーマを飲むと間接が滑らかになり、足の捻挫から守り、骨折しないとある。また当時馬肉を食べる風習があったことが伺える。流産から守る、死者を蘇生させる呪法の歌もある。2014/11/22
圓(まどか)🐦@多忙のためほぼ休止中
6
確かに物語性はないので詩として読んだけれど本当に読み終えるまでに時間はかかったし、しかもほとんど頭に残っていない。この本に登場した名前に関連する話を知っていればもう少し楽しめたかもしれないけれどと思うと惜しい。ゲーマーとしてはかつて自分が遊んだゲームでお目にかかった名前がちらほらで、ヴリトラとか出典ここだったのかみたいな無駄知識は得られました。仏像に詳しければここに登場する神が巡り巡って形を変えて日本の神にもなって信仰されていると思うと歴史の流れで感慨深いものがあるかな2019/04/09
-
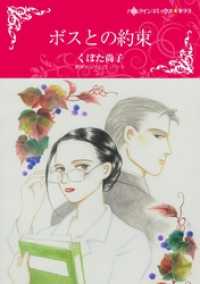
- 電子書籍
- ボスとの約束【分冊】 1巻 ハーレクイ…
-
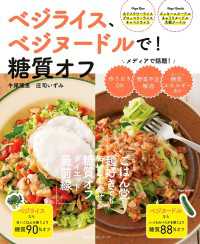
- 電子書籍
- ベジライス、ベジヌードルで!糖質オフ …




