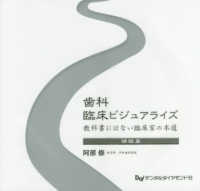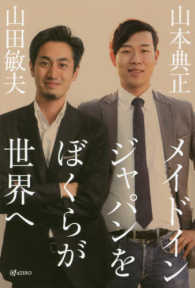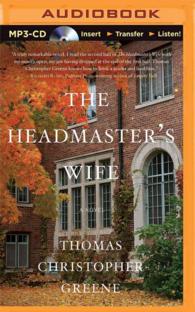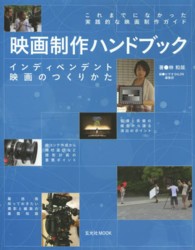出版社内容情報
表題作は,多くの近代日本の文学者に題材をとりながら,日本人の生き方を,調和型・上昇型・下降型・逃避型・立身出世型に分類し,それらを巧みな例で実証する.昭和二十八年発表当時大きな反響をよび起した論文であり,著者の思想の集大成として高く評価されている.他に「近代日本の作家の生活」等を収録. (解説 奥野健男)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
17
漱石の波紋は大きいようだ。野上弥生子、芥川竜之介、内田百閒、和辻哲郎。それに、学習院出には、有島武郎、武者小路実篤、志賀直哉、里見弴(とん)らがいる(19頁)。「日本の民衆は、自己放棄の仏教的衝動によって、可能な限り屈服し後退する。しかし、どうしても生きれないと感じたとき、彼らは爆発的に絶望的に抵抗する」(35頁)。現代では、原発再稼働反対デモもそうした類なのかもしれない。福澤諭吉はいかなる事業も失敗した場合を考えて大胆に実行した(68頁)。志賀直哉の考え方に近いようだ。2013/08/14
lily
15
近代日本文学を知るなら、楽しみたいなら、強烈な電気ショックを浴びたいなら伊藤整は外せないはず。文壇の膿を出し切る仕事に成功した稀有な存在。紅葉のゴーストライター人生、消された芸術家作家、出版社の変貌、偽りの愛の輸入など、非常にありがたい暴露の嵐。2019/06/16
とまと
15
「近代日本における『愛』の虚偽」キリスト教には、他人を同様のものと考えて愛せ、という考え方がある。一方、それに近い考え方として、儒教の仁、仏教の慈悲がある。前者には、絶対者の存在があり、他者への愛すなわち人間には成し得ないことを命令・強制する。つまり、成し得ないことに実在性を持たせているのが宗教の力であって、信仰がないときに「愛」という言葉を持ち込むことには「虚偽」がある。明治以来、我々は「愛」という言葉のみ輸入し、祈りや懺悔(キリスト教の救済性)は取り入れてこなかった。2013/08/30
フリウリ
10
均一本からのサルベージ。以前に読んだ時は決してそうは思わなかったはずですが、例えば、西洋人は人間関係のなかで安らげるが、日本人は孤独のほうが安らげる、というような比較文化的な文章を読むと、特に21世紀以降の人間(人類)の平均化(平板化?)は凄まじく、そのせいもあってか本書でいう文学的な「発想の諸形式」は、日本語社会に限らない普遍性があるような気がしました。図式的によくまとまっているので、19世紀以降の文学を読む人、社会と文学の関係に関心のある人にとっては、参考になると思います。82024/01/13
colocolokenta
9
出版されたのが昭和28年。江戸末期からそれまでの文学史が述べられている。日本文学における私小説というものの位置づけが理解できる。藤村、太宰などは、「やるぞ、やるぞ」と読者が期待し、その通りの結末を迎えた、という話を聞いたことがあるが、そういうことだったのかと。近代日本人の生き方とまではいかず、オピニオンリーダーとしての近代日本人作家の分析として読んだ。 所詮文壇という狭い世界の中にしか生きていない、という点では、作家も、医者も、その他の世界に住む人間もみな同じである。2013/06/23