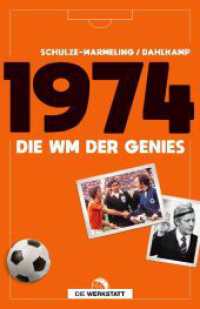出版社内容情報
道元についても,禅宗についても,「幼児に等しい無智」であった著者が,ふとした機縁でこの巨人の生涯と格闘することになる.文献を渉猟し,自分の頭で読み解いてゆく――禅師七百回忌の「饅頭本」で終らせないためにも「見て来たような嘘」だけはつかない,と語る作家里見〓(一八八八―一九八三)の描いた道元禅師像. (解説 水上勉)
内容説明
道元についても、禅宗についても、「幼児に等しい無智」であった著者が、ふとした機縁でこの巨人の生涯と格闘することになる。文献を渉猟し、自分の頭で読み解いてゆく―。禅師七百回忌の「饅頭本」で終らせないためにも「見て来たような嘘」だけはつかない、と語る作家里見〓(とん)(1888‐1983)の描く道元禅師像。
目次
敢行と断念と
七百年
縦棒上の点
横棒上の点
誕生・幼時
母の死・受戒
教学時代
参禅・入宋
正師の鉗鎚
深草隠棲
当処永平
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
17
「読史眼」とは、書かれた事実の表面(うわべ)ばかりでなく、その裏なる、書き人(て)の心理までも窺い知る、「紙背に徹する」底の眼力を指して言う(23頁)。洞察力を読書に適用することの意義か。両性具有の話も出てくる(73頁)。これは、中性化社会という言葉を初めて植田一三氏の明日香出版社の本で知った。女性的性情の勝った男、男性的性情を含んだ女が出てくる。必ずしも明確な線引きをできないのが人間であると思える。1241年に彼は42歳にして、『正法眼蔵』第7~11章まで制作(230頁)。一方、私は読書案内本を編んだ。2013/10/15
moonanddai
7
「只管打勉」相当昔、井上ひさしさんにサインと一緒に書いていただいた言葉、ですけど、今のこの体たらく…。それにしてもこの手の本を読んで思うのですが、宗教とは畢竟「生き方」のあり方なのでしょう。とは言え「善と思い悪しと思うことを棄てて」「仏祖の言語行履に従い行く」ことになるらしいのですが、で、実際どうする?それならいっそ「溺れる者は藁をもつかむ」的に称名念仏のほうが「分かりがいい」のですが、それも「春の田の蛙の昼夜に鳴るがごとし」となってしまう。作麼生。2017/11/17
烟々羅
5
兄弟のなかの、後世に有名でないほうの文士、里見弴。 ……て言いつつ、心中で有名になった兄・有島武郎の文章は今でいえば中二病、アタマで書いた文章だし、弴さんの文章は肚で書いてある。先だって没された山本夏彦さんと同様、べらんめぇな口調が目に浮かぶ。 高校生だったか、その後だったかに、長すぎて読むの疲れて一度しか読めなかった「多情仏心」の節々が思い起こされ、改めて書店を探していてついでに見つかったのがこれ。 仏教の偉人伝でもべらんめぇ調。主題に似合わないだろ、と普通は思う。逆だ。弴さんは一貫して「仏教だ、悟りだ2012/01/21
Bevel
5
すごい読んでて心地良かった。道元って難しいからめんどい、という里見さんの気持ちが滲みでてる前三分の一だけれど、そのあと道元が宋にたどり着いたあたりからは、もう腹をくくったと見えて、様々な文献を自分なりに噛み砕いて、丁寧に、わかった顔をしないで、教えてくれる。四字熟語や漢語がたくさんでてくるのに、全然読みにくくなかった。すんごい不思議。こんな文章書く人他に知らない。2009/11/28
風鈴
2
すいません、ギブです。でも160ページくらいまでは頑張ったので、えらい!!(自分を褒めてくスタイル)最初四分の1は書くに至った理由とかで、残りは道元同士の生い立ちに沿って、いろんな文献と想像するだにこうなのでは?という進め方。文章の話にも出てきた縦の線と横の線の概念がここでも登場。先に読んでおいて良かった。それとめっちゃ調べてくれてる弟子えらい。途中に出てきた「2年前のお別れ」がより具体的な示唆がなくて、めっちゃ気になる(道元道士の親が亡くなったところ)。詳しい人ならわかるかも。いつかリベンジするよ!2021/03/19
-

- 電子書籍
- 二重×監禁~二重人格のヤンデレ男に監禁…
-

- 電子書籍
- ヤンキーJKクズハナちゃん 25 少年…