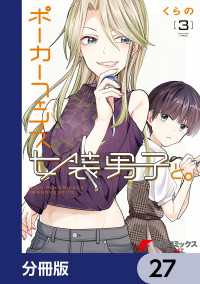出版社内容情報
明治四十三年の盛夏,漱石は保養さきの修善寺温泉で胃潰瘍の悪化から「大きな動物の肝の如き」血塊を吐いて人事不省におちいった.辛くも生還しえた悦びをかみしめつつこの大患前後の体験と思索を記録したのが表題作である.他に二葉亭四迷・正岡子規との交友記など七篇.どの一篇も読む者の胸に切々と迫って来る. (解説 竹盛天雄)
内容説明
明治43年の盛夏、漱石は保養先の修善寺で胃潰瘍の悪化から血を吐いて人事不省に陥った。辛くも生還しえた悦びをかみしめつつこの大患前後の体験と思索を記録したのが表題作である。他に二葉亭や子規との交友記など七篇。
目次
思い出す事など
長谷川君と余
子規の画
ケーベル先生
ケーベル先生の告別
戦争から来た行違い
変な音
三山居士
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





TERU’S本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
クプクプ
72
随筆集です。「思い出す事など」は再読でしたが、私も年齢を重ねたせいか、漢詩や細部のセリフが、心に響きました。ラストは忘れていて、意外に感じました。夏目漱石は病に倒れて自然を求めましたが、その自然も人間の背景にあってこそ、という表現には、自分もハッと気づき反省しました。「長谷川君と余」の長谷川君とは二葉亭四迷のことで、読んで勉強になりましたし今後、二葉亭四迷の作品も機会があったら読もうと感じました。「子規の画」も、子規が漱石に欠点を隠していたことがわかり、この随筆も後世に残るとは予想していなかったでしょう。2025/03/14
Gotoran
61
標題『思い出す事など』他、ほぼ同時期に書かれた随筆7篇を収録。メインは、修善寺の大患に関わる闘病記で、胃潰瘍の悪化から修善寺で保養することになった時のことで、静謐な筆致で綴られていて、当時の漱石の心境は静かで透明、吐血での苦しみがあったにも拘らず…漱石自らが経験した苦しみや生死への諦観など主題が陰鬱ではあるものの、心に沁みる文章を垣間見ることが出来た。2022/07/03
涼
57
http://naym1.cocolog-nifty.com/tetsuya/2024/06/post-b55e31.html 子規の絵をけなしつつ、漱石の子規への愛が伝わってくる【子規の画】が好きです。2024/06/22
Mijas
52
修善寺の大患後、死と向き合った体験がこれ程までに明晰な文章で表現されていることに驚く。特に漱石の言語感覚の秀逸さが際立つのが「思い出す事など」に収められている漢詩の数々。白文なので『漱石の漢詩』(松岡譲編著)の書き下し文を参照し、漱石の風流の境地を伺い知ることができた。病中、大空や碧山、一片の花に、心の無限の静かさが表現される。それは「縹渺とでも形容してよい気分だった」。死に直面したドフトエフスキーの恍惚状態をあげ、自分も共に病に対しての感謝と人々への感謝の念を述べる。生への悦びが素直に伝わってくる。2016/08/27
ころこ
32
大病を患った後、死について考える漱石の一連のエッセイで記されるのは、周囲の人々の死です。療養の労を取り計らった医師の方が急逝し、著作の影響を受けたジェームズ博士も病床で前後不覚の間に世を去っています。人間は死を経験できないので、死を意識して生を考えるというのがタイトルに込められています。病床で原稿を書くことを叱責していた朝日新聞主筆の池辺三山も、巻末の文章では弔辞が述べられます。ここでも池辺の生前最後の姿を自らに重ねるような筆致になっています。2020/03/19