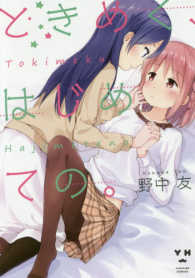出版社内容情報
平安中期ないし末期に成立した長文の序をもつ古詩.老いさらばえて町を徘徊する女が,往時の贅沢の限りと親兄弟の死によって零落し悲惨をきわめる老境を綿々と語る.この物語の主人公は小野小町ではないが,小町の物語として読みつがれてきて,小町像の形成に多大の影響を与えてきた.原文・読み下し文・現代語訳に詳細な注を付す.
内容説明
平安中期ないし末期に成立した長文の序をもつ古詩。老いさらばえて町を徘徊する女が、往時の贅沢の限りと親兄弟の死によって零落し悲惨をきわめる老境を綿々と語る。この物語の主人公は小野小町ではないが、小町の物語として読みつがれてきており、小町像の形成に多大の影響を与えてきた。原文、読み下し文、現代語訳に詳細な注を付す。
目次
玉造小町子壮衰書
付1 玉造小町子壮衰書(影印)
付2 九想詩(影印)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
121
底本は建長年間頃書写の九条家旧蔵東京大学国文研究室本『玉造小町子壮衰書』。成立は平安中期~末期。長い序と、それに続く五言の260句に及ぶ詩から成る。詩は多分に修辞的で、さほど面白みを感じないが、序は小町(明記はされていない)と思しき主人公の栄華と落魄とをつぶさに語り、きわめて興味深い。背後には、浄土思想が顕わなのだが、それを突き破るような形象さえ見受けられる。ことに「壮」において、数々の珍味が羅列されるあたりは興味が尽きない。現代語訳も付されているが、ここはやはり、原文で漢文のリズムと格調とを味わいたい。2014/05/09
新地学@児童書病発動中
89
若い時は華やかな人生を過ごした女性が、老いと病により、零泊し、町を彷徨う姿を描き出した漢詩。ここに描かれている女性は、小野小町伝説のもとになったそうだ。詩の後半では、仏教による救いが描かれているが、私は人間の苦しみを描いた前半の方が印象に残った。若くて溌剌した時代はあっという間に過ぎ去り、貧困や病、他人との不仲と言った苦しみが押し寄せてくる。それでも生きていかなければならない。人間の無常が身に沁みる。やや美文に流れるところがあるが、硬質の詩情を湛えたこの韻文は繰り返し読みたくなる力を持っていると思う。2017/10/08
まさ
26
小町の生涯を知りたくて手にした書。主人公は小町ではないが、"小町像"に影響を与えているそう。長文ではあるけど、読み下し文を心地よく読み進めることができた。その後、口語訳で再読。若い頃は贅沢贅を尽くした女性がその後凋落の人生を歩む。決して本人が高慢というわけではなく、身分等で人生が左右されるその時代が見えてくる。浄土思想と無常観を軸に読むと壮衰の「壮」の部分に人生への執着すら感じるが、それはそれで興味深い。2021/05/15
双海(ふたみ)
12
平安中期ないし末期に成立した長文の序をもつ古詩。老いさらばえて町を徘徊する女が、往時の贅沢の限りと親兄弟の死によって零落し悲惨をきわめる老境を綿々と語る。この物語の主人公は小野小町ではないが、小町の物語として読みつがれてきて、小町像の形成に多大の影響を与えてきた(カバー解説より)。影印が載っているのは嬉しいです。見ていると楽しい。2014/03/22
あめこ
2
大学の演習で使用。初めて玉造小町子壮衰書の存在を知りました。演習苦戦したなぁ・・・・・・。2014/01/14
-
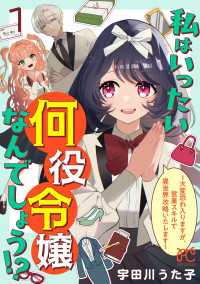
- 電子書籍
- 私はいったい何役令嬢なんでしょう!?~…