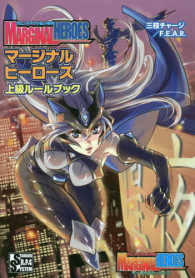出版社内容情報
2022年3月、培養ステーキ肉が日本で試食された! 食料不足などを背景に登場、期待の一方、不安もある培養肉は、種類がいろいろ、作製技術も異なる。ウシのステーキ様肉作製に成功した著者が、用いられた先端技術と将来の可能性を、社会の受け入れを検証する著者が課題を、最低限の基礎知識としてまとめた超入門書。
内容説明
2022年3月、培養ステーキ肉が日本で試食された!食料不足などを背景に登場、期待の一方、不安もある培養肉は、種類がいろいろ、作製技術も異なる。ウシのステーキ様肉作製に成功した著者が、用いられた先端技術と将来の可能性を、社会の受け入れを検証する著者が課題を、最低限の基礎知識としてまとめた超入門書。
目次
第1章 なぜ今、培養肉なのか?
第2章 培養肉のつくり方
第3章 培養肉への期待と不安
第4章 立ちはだかるハードルの数々
著者等紹介
竹内昌治[タケウチショウジ]
2000年東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻博士課程修了。東京大学生産技術研究所講師、准教授などを経て、東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授
日比野愛子[ヒビノアイコ]
2006年京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。弘前大学人文社会科学部准教授などを経て、教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
shikada
17
培養肉(人工肉)について解説する一冊。従来の畜産には問題点が多い。急増する世界人口に対して供給がたりない、温室効果ガスの排出や水の消費も多く環境負荷が高い、家畜間の感染症・薬剤耐性菌も多い、動物愛護の観点など。こうした問題から、培養肉へ注目が集まっている。培養肉には味と食感だけ似せることを目指すミンチ肉と、筋繊維まで再現するステーキ肉がある。培養肉を「不自然だ」として食べたくない層がいるらしいけど、普及したら誰もそんなこと言わなくなると思う。カニカマはカニの肉じゃないけど「不自然だ」なんて言う人はいない。2022/12/20
ももいろ☆モンゴリラン
2
『肉は美し』で動物倫理とか食肉に興味が出てきていま発注した本が届くの待ち。手元にあったぜ培養肉。「畜肉か人肉か?」なんて二極化なんてしなくてもソイミートとかハイブリッド肉とか私達には多様的でグラデーションな選択肢があるハズじゃん…!① 説明はブックレットなので大変割愛されてるみたいなので、抽象化された「肉」を培養している感を受けそれはそれでSFみ。希少部位の大量生産とかできるようになったら夢ですね。でもディストピア脳は「培地はシャーレの中だけで済むのかな」とも思ってしまいます…2025/11/24
つみれ
1
2021年に2020年出版の『クリーンミート 培養肉が世界を変える』を読んで、凄く面白かったけど、最新情報を日本語でキャッチアップするのが難しいんだよな〜と思っていたら、丁度その頃急に日本の報道で培養肉が取り上げられるようになって、その辺のまとめが書かれてる感じ。ハイブリッド肉が現在の主流なのは知らなかった、確かに現在の技術で美味しいものが欲しいだけならそれでいいよな。ステーキを待たずともカルビと豚バラがあれば…いやモツとかハツとかも欲しいよな。2023/07/26
中村蓮
0
培養肉を作る仕組みや課題など現在地点(日進月歩の世の中で1年前のものですが)が分かりました。 技術的な話はあまり詳しく書かれているのは珍しいと思いました。2023/11/24
-
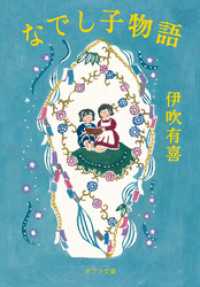
- 電子書籍
- なでし子物語 ポプラ文庫 日本文学